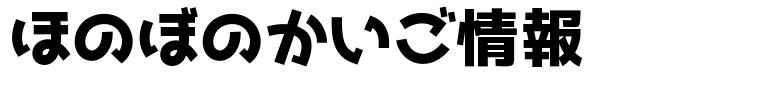投稿者のしんです。
私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。
その後かれこれ10年以上、介護現場で働いています。
2年~3年で、1つの部署を異動してきました。
特別養護老人ホーム、グループホーム、ショートステイをこれまで経験し、今に至ります。
今後のキャリアとしては、「しろくま介護ナビ」を利用して、在宅施設のサービスを経験していく予定です。
日本の介護の現状と課題を、施設介護の観点から学びたいと思っております。
-

-
しろくま介護ナビはどんなサイト?
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後かれこれ10年 ...
続きを見る
介護をするうえで、「人間関係」の悩みは、必ずつきまといます。
私は、長年、介護現場で多くの失敗をしてきました。
その経験を通して、お伝えできることがあります。
こちらの記事で少し楽になると思います(^^)
-

-
人間関係で悩まれている方へ
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後かれこれ10年 ...
続きを見る
この記事では、認知症の方とのコミュニケーションについて書いていきたいと思います。
初めて介護に携わられた方や、コミュニケーションが苦手な方にとっては、
認知症の方と、どう接したら良いのか悩まれることだと思います。
コミュニケーションが上手くなると、介護職がより楽しい仕事になります。
- ご利用者に対して、苦手意識をもたなくなる
- 1人1人のご利用者のニーズを聞き出しやすくなる
介護に慣れた方でも、認知症の症状に対する対応に慣れていない方もおられると思います。
日頃の仕事の参考にして頂けると思います。
~もくじ~
【認知症】言葉で会話すること以上に大切なコミュニケーション

コミュニケーションというものは、幅広い捉え方をすることができます。
- 何気ない雑談
- ご利用者からの相談
- 介護者からの声かけ
これら全てが、コミュニケーションといわれるものになります。
つまり、コミュニケーションは普段から私たちが何気なくしている行為です。
では、介護職として働くうえで、なぜコミュニケーションが難しいものとされるのでしょう。
その一番の原因は、相手の気持ちが分からないことにあります。
基本的に、心の中で思っていることは、口にしないと相手には伝わりません。
- 過去の病気の後遺症の影響
- 現在患っている病気のの症状の影響
- 自分と相手との間に信頼関係ができていない
- 他人に弱音をみせたくない性格
さまざまな理由で、思いが伝わらない状況があります。
コミュニケーションに関しては、こちらの記事も参考にしてもらえると思います。
【参考1】コミュニケーション能力を上げたいなら聞き上手になれ!
【参考2】【会話が苦手な人むけ】伝え上手になる方法
コミュニケーションは、介護職にとって仕事道具と言っても過言ではありません。
それほど、重要なスキルです。
良いコミュニケーションをとるための技法はいくつかあります。
その技法の1つに「バリデーション」というものがあります。
バリデーションは、認知症の方と接する時の「マニュアル」のようなものとされています。
【認知症の方との関わり方】バリデーションとは一体なに?
バリデーションとは、ビジネス用語になります。
「検証、実証、認可、妥当性」の意味を持ちます。
IT、医薬、介護業界で使用され、現在では認知度も高まっています。
介護業界では、バリデーション療法と呼ばれることもあります。
「バリデーション」は、認知症の方に寄り添い共感することで、信頼関係をきずく方法です。
【バリデーション】14個のテクニックとその効果とは?

バリデーションには、14個のテクニックがあります。
これを使用することで、認知症の方の問題行動を共感して受け止める。
そして、症状が悪化するのを防ぐ効果があります。
具体的なテクニックは何があるの?
- 1. センタリング
- ケアをする方がイライラや不安を抱えていては、信頼を得ることはできません。
- まずは自分の心を落ち着かせて、認知症の方の気持ちを受け止められる状態にします。
- 2. オープンクエスチョン
- 認知症の方に「いつ」「どこで」「誰が」「どのように」「なぜ」といった質問をする。
- 3. リフレージング
- 認知症の方は自分が言ったことを、相手(介護者)が確認・認知してもらうことで安心します。
- 「お茶はいらない」と言われたら「お茶はいらないのですね」というように言葉を繰り返して会話をしましょう。
- 4. 極端な表現を使うようにする
- 最善・最悪など極端なケースを想像さえることで、現在の感情を和らげる。
- 5. 反対のことを想像させる
- 例えば認知症の方に「誰かが私のお茶を飲んだ」と理由もなく訴えられた場合、
「その人がお茶を飲まない時もあるんですか?」のような「はい/いいえ」で答えられない質問をします。 - その後に反対のことを想像してもらいます。
こうすることで認知症の方の過去の経験を思い起こさせ、物事を対処する方法を身につけることに効果があるとされています。
- 6. レミニシング
- 過去のことを尋ねて懐かしい思い出話をしてもらいましょう。
- 経験を思い出すことで自身の考え方を取り戻すきっかけになるのです。
- 7. 話を持続させる
- 場合によっては認知症の方の話を聞き取れないこともあります。
- そんなときは「それは面白いのですか?」「どんな人ですか?」など、あいまいな表現を使って会話を継続させることが大切です。
- 8. 好きな感覚を用いて会話をする
- 人にはそれぞれ好きな感覚(触覚・視覚・嗅覚など)があります。
- その人が感覚を連想しながら話せるよう、話題に感覚を用いましょう。
例えば「花はどんな色でしたか?」「どんな匂いでしたか?」「どんな手触りでしたか?」などです。
- 9. 親しみのあるアイコンタクトをする
- 高齢者は視界が狭くなっていることがあります。
- 視線を合わせることを意識して、長く見つめるようにしましょう。
- 10. はっきりと低く優しい声で話す
- 高い音は高齢者に聞こえづらいです。
- 低く落ち着いたトーンでゆっくりと話をしましょう。
- 11. タッチング
- 包むように触れるなど、スキンシップをとりましょう。
- 12. 音楽を用いる
- 認知症の方が好きだった曲を一緒に歌ったり、流しながら会話をしたり過去の話を聞きましょう。
- 13. ミラーリング
- 相手の表情や仕草、口調をさりげなく真似します。
- このミラーリングを行うことで、無意識に親近感が湧くようになります。
- 14. 満たされていない人間的欲求と行動を結びつける
- 行動や言動からどんな欲求が隠れているのか考えましょう。
- 「愛されたい」「人の役に立ちたい」などの欲求を知ることで適切な対応が取れるようになります。
【引用記事】ネクサスコート:認知症の方に共感して接する「バリデーション療法」とは
これらが、バリデーションの技法になります。
こういう接し方が、認知症の方への対応として求められます。

- 専門用語が多くて、よく分からない・・。
- こんなのできる気がしない。
- そもそも覚えられない。
こう感じますよね(笑)
でも、大丈夫です。
日頃みなさんが、認知症の方と接している時を思い出してみて下さい。
おそらく、これまでバリデーションを知らなかった方でも、どれかの方法を使ったことがあると思います。
- あぁ、あの時の対応はこれかも!
- そういや、あの時これをしていたな。
- これよく使ってるかも・・。

私も、これらの中に覚えている技法もありますが、全部は覚えられません。
しかし、よく使っている技法はいくつかあります。
自称真面目な私の真面目すぎた失敗談

私もこれまでに、認知症の方とのコミュニケーションに悩んだ経験があります。
その時にバリデーションという技法と出会いました。
そんな私は、「明日から実践しよう!」と意気込んで職場へ。
その結果・・・。
- ストレスを抱えたまま対応 ➡ 相手の行動を急かし、相手を怒らせる
- オープンクエスチョンだ! ➡ 「うるさい!」と怒られる
- リフレージングを駆使しよう! ➡ 「あんた、人の話聞いているか!?」と怒られる。
- ミラーリングに挑戦! ➡ あからさますぎて、自分で笑ってしまう
これら以外にも、数え切れないほど失敗して、これまで相手を怒らせていました。
不器用というのか・・・。
頭が悪いというのか・・・。
今では、良い思い出ですけどね(笑)
参考書や書籍等で覚えたことを直球で使おうとしてしまう
私が失敗する時は、だいたいこれでした。
【過去の失敗を教訓に】今の私が意識して使っているコミュニケーション方法
これまで多くのご利用者と接してきて、多くの失敗をしてきました。
その私が、今ご利用者と接する時、必ず意識していることをご紹介します。
- 話しかけられたら、忙しくても手をとめる。
- 話を聞く時の「表情」を意識する。
- 相手が受け取りやすい言葉を選択する。
- タッチング
- 「言葉を返す」or「見守りに専念する(見守り時の表情も意識)」
- 「相手がそうなら、そう」という感覚をもつ。
この6つは、必ず意識します。
体に染み込みすぎて、無意識でもできていると思っています。
話しかけられたら、忙しくても手をとめる
業務に入っている時は、基本的に忙しいです。
その状況で話しかけられても、必ず、手をとめ相手の方を向き話を聞くようにしています。
注意ポイント
話を聞く時の「表情」を意識する
認知症の方と話をする時は、特に意識しています。
認知症は進行すると、言語の理解や認識ができなくなってしまいます。
しかし、「感情」を失うわけではありません。
表情や声のトーンや大きさだけでも、相手に与える印象はとても大きいです。
注意ポイント
ご利用者が受け取りやすい言葉を選択する
これは、相手の気持ちを推測する必要があります。
相手が楽しそうな時と悲しそうな時、声かけの仕方は変わりますよね。
また、混乱されていたり、ソワソワされている時は、相手に余裕がない状態です。
普段と同じ声かけは、届かないと思います。
その時は、相手が、こちらの声かけを受け取りやすい状態になってもらうのを先決します。
相手の置かれている状態を、しっかりと観察することが大切です。
【参考】「観察力」がない介護職員は不幸になる【介護を楽しみたいなら必ず必要です】
相手がよく使っている言葉を使うことも良い方法
方言まで真似するのは難しいですが、相手がよく使う単語や言い方を使うことで、
相手が言葉を受け取った時に、イメージしやすくなります。
伝わりにくい時は、そういった単語を探すこともします。
- トイレを指す言葉:「お手洗い、ご不浄、トイレ」等
- うがいを指す言葉:「うがい、ぐじゅぐじゅぺー」等
注意ポイント
タッチングを使う
これは、背中をさすったり、肩を軽くポンポンとしたりします。
辛い時でも「側にいるよ」という気持ちを伝えたい時等に使います。
「言葉を返す」or「見守りに専念する(見守り時の表情も意識)」
相手の状態に合わせ、これを判断します。
上でも説明しましたが、相手がこちらの声を受け取りずらい環境にいる場合、
こちらが横からごちゃごちゃ言っても、「うるさい」と印象を与えるだけです。
事故が起こらないように注意し、少し相手から離れ、そっと見守ることも重要です。
もし、相手が振り返った時、目が合ったら、相手の言動から気持ちを察して、表情をつくります。
「相手がそう言うなら、そう」という感覚をもつ
認知症の方を対応されている方で、よく相手の訴えを訂正しようとされる方がいます。
- 私ご飯食べてないんやけど
- 誰か知らん人に物を盗られた
認知症の方が話しているのを聞いたことがある人も多いと思います。
認知症の方のそういった訴えに対して、「食べましたよ!」「誰も盗ってません」と言われる職員もいますが、
そういった方は、認知症についての知識が不足しています。
認知症の方は、エピソードごと記憶から抜け落ちてしまうので、
ご本人からすると言っていることは、「事実」です。
「相手がそう言うなら、そう」という感覚を持ちましょう。
訴えに対する対応を考えるのは、それが前提です。
認知症の方と接する時は、その方の世界観を理解することが重要だといわれます。
それは、その通りです。
介護者の常識に相手を当てはめて観てしまうと、分かってあげられる気持ちも分かってあげられません。
注意ポイント
- 「ご飯を食べていないと思っているのは、本人の中での事実」
- だからどうする?
この視点でケアを考えていくことが大切です。
おわりに
この記事では、認知症の方との会話で意識すべきことについて、
書いてきました。
いかがだったでしょうか?
コミュニケーションは、相手との信頼関係を築くための手段です。
より良いケアをしていくためには、いかにコミュニケーションの質を上げるか。
これも大切なことです。
認知症の方は、症状が進行すると、言語の理解する機能が低下します。
- 自分の思いを相手に正確に伝えることが難しくなる。
- 介護者からの言葉を理解するのが難しくなる。
介護をする側もどうやって、接していけば分からないこともあると思います。
しかし、「感情」は必ず伝わります。
介護者が、相手に、少しでも安心してもらえるような存在になるためには、
言葉以外の「表情」や「仕草」などをいかに意識するか。
言葉で会話する以上に、表情で会話することが大切です(^^)
-

-
介護職の給料事情「新人の給料」と「介護歴10年の給料」を比較
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ...
-

-
【断言します】仕事を辞めてもすぐに次の職場は見つかります
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ...
-

-
どうにかこの辛い毎日を抜け出したい・・・。【介護職の転職】
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ...
-

-
【体の疲れがとれない方むけ】あなたの体を一番知っているのはあなた自身
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ...
-

-
【社畜人生から抜け出そう!】ブラックな介護施設14つの特徴と対策【現役介護士が解説します】
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後かれこれ10年 ...
-

-
「私もあんな風になるの?」認知症の本人が不安な思いを告白
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ...
-

-
介護施設に潜む闇:若い芽をつむお局さまの言動6選と攻略方法
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ...
-

-
【ほんまでっかTVから学ぶ】認知症ケアに活かせる対応方法
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ...
-

-
【介護職あるある】職員(先輩)により介助の「やり方」が違う
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ...
-

-
【みんな同じ時間に介助?】排泄介助にも個別性を求めましょう!
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ...
最後まで読んで頂きありがとうございました(^^)
良い記事だなと感じて頂けましたら。
- いいね!
- シェア
お願いします♬
※TOPページから、メールアドレスを登録して頂けますと、最新記事がいち早くメールで届くようになります。