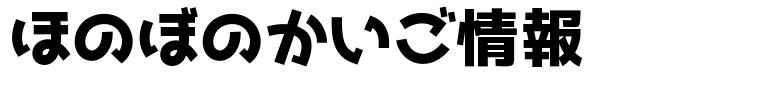投稿者のしんです。
私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。
その後かれこれ10年以上、介護現場で働いています。
2年~3年で、1つの部署を異動してきました。
特別養護老人ホーム、グループホーム、ショートステイをこれまで経験し、今に至ります。
今後のキャリアとしては、「しろくま介護ナビ」を利用して、在宅施設のサービスを経験していく予定です。
日本の介護の現状と課題を、施設介護の観点から学びたいと思っております。
-

-
しろくま介護ナビはどんなサイト?
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後かれこれ10年 ...
続きを見る
介護をするうえで、「人間関係」の悩みは、必ずつきまといます。
私は、長年、介護現場で多くの失敗をしてきました。
その経験を通して、お伝えできることがあります。
こちらの記事で少し楽になると思います(^^)
-

-
人間関係で悩まれている方へ
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後かれこれ10年 ...
続きを見る
介護職が大変な仕事と言われるのには、
さまざまな要因があります。
- 身体を痛めやすい(身体介助面など)
- 精神的に疲れやすい(ご利用者の言動、職員間の人間関係など)
- 生活リズムが崩れやすい(シフト制の勤務、夜勤など)
介護者も人間です。
介護者も嫌でも年をとります。
その日のうちに体の疲れが全てリセットできたら、
どんなに素晴らしいことか!
私自身も日々そう思い生活しています。
私もこれまで現場で10年以上経験してきました。
いろいろなことを試し、今では体調を大きく崩すことなく、
介護に従事できています。
そんな私の経験をもとに、お伝えしていきます。
~もくじ~
【体の疲れがとれない方むけ】あなたの体を一番知っているのはあなた自身

みなさんは、日々体の疲れがしっかりとれていますか?
介護職と言えば、
- 腰の痛み(ヘルニア)
- 膝の痛み
- 手の指の腱鞘炎
- 頭痛
- 精神的疲労
- その他、ホルモンバランスが崩れる等の体調不良
これらが付き物みたいになっていますよね。
介護職に限ったものでないですが、
それでも「介護職ならでは」の痛め方をする時もあります。
普段生活していても、体を痛めることはあります。
では、なぜ治療するまでに悪化してしまうのでしょう?
体を痛めてしまうのは「日々の蓄積」が原因
生きていれば、体に疲れは溜まります。
治療するまでに悪化してしまう原因は、
その疲れを、日々蓄積してしまっているからです。
腰痛を例にしてお伝えします
腰痛は、介護職にとって「発生しやすい」体の痛みですよね。
- 体に負担のかかる介助方法や、日頃の姿勢の悪さで腰に疲れがでる
- 解消できず、疲れが溜まっていく
- ある日、普段通り仕事している中で、腰を痛める(ぎっくり腰など)
- または、ずっと慢性的に腰が重い感じが続く
このような流れになります。
介護者が腰痛を発症する原因として、
- 筋力低下
- 柔軟性の低下
この2つが大きく関係していると言われています。 みなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 この記事では、「腰痛」をテーマに書いていきたいと思います。 介護をしてい ... 続きを見る
ちなみに、腰痛を発症者で一番多いといわれているのは、
20代で、介護経験3年未満の方です。
腰痛について、詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ。

「腰痛」について理解しよう
私は、20代後半で「腰痛」を発症しました。
あの時は、靴下をはくために下を向くだけで激痛でした・・・。
治療には、3か月もかかりました(-_-;)

注意ポイント
【私の経験を通して】悪化させないために、日々意識すること
「身体的な疲労」と「精神的な疲労」の2つに分け、ご紹介します。
これが、日頃からできているかできていないで、大きく変わります。
- 日頃の介助方法を見直す
- 日頃の姿勢を正す
- 仕事から帰った後に体のメンテナンスをする
- 寝具を変更する
- 仕事中にイライラしたら、誰もいない場所で深呼吸する
- しんどい時の働き方を覚える
- 頭(脳)にかかる疲れを減らす
- 相談できる人を見つけておく
- 働き方を変える
順番に説明していきますね。
身体的な疲れに対して【自信をもっておすすめします】

➀ 日頃の介助方法を見直す
みなさんは、日頃どのような介助方法をしていますか?
「ご利用者による」。
その通りです。
しかし
介助する際、無駄な動きをしている介護者は、かなりおられます。
また、正しい介助方法を身につけるのも一つですが、
それと同等に、それ以上に必要なのは、「対象者の動き」を観察することです。
特に、「立位動作の介助」「移乗介助」は、間違えるとすぐに腰痛です!
介助方法については、こちらから見てみて下さい。
(今後も記事を更新していきます)
➁ 日頃の姿勢を正す
現代は、スマホやパソコンで目を酷使するだけでなく、
猫背など姿勢が崩れている人も、以前に比べかなり増えているようです。
私自身も猫背なので、これは意識しました。
しかし、なかなか意識だけで治るほど簡単ではないんですよね・・。
そのため私は、下のグッズを使っています。
- 1日の姿勢を伸ばすことで、ストレッチできます。
- 付けながら、他の用事ができるので、帰ったらつけてます。
- 仕事中も、プライベートも終日つけています。
- 肩こりの悩みは卒業しました。
いろいろ試して、これらに行きつきました(^^)
私は、難病の「円錐角膜」という目の病気です。
毎日、頭痛がひどく吐き気などもありました。
コラントッテ(Colantotte)を使い始めたら、全くなくなりました。
その経験もあるので、「肩こり」で悩んでいる人には、本当におすすめします。
➂ 仕事から帰った後に体のメンテナンスをする
仕事終わりは、すごく疲れていますよね。
その時の体の状態は、筋肉が冷え、固まっている状態です。
そのため、私はお風呂に入り体を温めた後、体の筋肉をほぐします。
その後、下記のものを使います。
ソファに座りテレビを見ながら、携帯を見ながら使えるので、とても便利です。
➃ 寝具を変更する
寝具はとても大事です。
実は私も最初、半信半疑でした。
寝具を変えたのは、引っ越しがきっかけでした。
「新しい家具を購入したから、ついでに・・・」
という感じでした。
商品が家に届き、試しにその夜寝てみたら、13時間寝てました(笑)
当たり前ですが、そんなに寝たのは初めてです。
起きたら、腰も痛くなく、頭の疲れが吹っ飛んでました(笑)
これまで甘くみてましたが、寝具って大切だと身にしみました・・・。
精神的な疲れに対して【仕事は人生を楽しむための手段】

➀ 仕事中にイライラしたら、誰もいない場所で深呼吸する
誰でもイライラすることはあります。
業務を回そうとバタバタしている時に、狙ったかのように
荒れるご利用者。
「もう!」となる気持ちもよく分かります。
そんな時は、私は誰もいない居室などに入ります。
そして、目をつむり、ゆっくり深呼吸します。
これは、アンガーマネジメントというものですが、
怒りは人間を感情的に、衝動的にさせます。
しかし、それは6秒間だと言われています。
その時間をすぎれば、怒りは収まります。
さらに詳しく
注意ポイント
- イライラすることは誰にでもあります。
「イライラしている自分を、いかに認識するか」
これが大切です。
➁ しんどい時の働き方を覚える
年中無休、元気いっぱいに働くのが一番良いとは思います。
しかし、私は、そんなことはまず無理だと思っています。
元気な時もあれば、しんどい時もある
それが人間です。
特に何も思いませんが、問題はしんどいと感じる時期です。
そんな時は、多くのことを後ろ向きに捉えてしまい、
他人の悪い所に目がとまりやすくなります。
自分に余裕がない時期に、他人に注意した時には、
自分も万全ではないので、もめやすくもなります。
それでも注意しなければいけない時は、注意する前に、
「注意する場所・言い方・周囲の状況等」をすごく計画をたてます。
また、普段の仕事では、事故なく仕事をすすめることのみに意識します。
基本的に私は、しんどさを感じない時期は、
「どうしたら、より良いケアができるか」を常に考えています。
しかし、それを考えるのを辞めるようにしています。

➂ 頭(脳)にかかる疲れを減らす
疲労には、「精神的(頭)の疲労」というものがあります。
これは、悩み事などを頭で考えすぎることで、疲れがとれず、
身体の疲れにつながると言われています。
常に悩みを頭で考えていて、考えすぎた結果、脳が過度に疲労してしまう。
そのため、脳にアデノシンという物質が溜まります。
アデノシンとは、ストレスや疲れを感じた時に出る物質です。
このアデノシンが溜まることで、ドーパミン(やる気ホルモン)を出にくくします。
つまり、ストレス(アデノシン)を抑制することで、やる気(ドーパミン)が出るということです。
ポイント
- コーヒー
- エナジードリンク(レッドブル、モンスター等)
これらには、カフェインが入っています。
カフェインの取りすぎは、頭痛等を引き起こすので、注意してくださいね。
アデノシンを脳から取り除く方法は?
アデノシンは、「睡眠」にも深く関係しています。
アデノシンは睡眠物質の1つ言われています。
睡眠をとらなければ、アデノシンは溜まっていきます。
しかし、寝ればアデノシンが減るという研究データもあります。
十分な睡眠は、脳を休ませるためにも必ず必要です。
【参考】脳との関係から解き明かす睡眠の謎とメカニズム
➃ 相談できる人を見つけておく
悩み続けていたり、考えすぎたりしていると、どうしても一人で抱え込んでしまいます。
しかし、一人で悩み続けても、現状を打破するのは難しいことが多いです。
そういう時は、誰かの力を借りましょう。
身内、友人、職場の人。
信頼できる人が一人でもいると、気持ち的にもだいぶ違います。
愚痴や文句を言うことも、時には必要です。
言うことで、すっきりすることもありますからね(^^)
➄ 環境を変える
体調を崩してまで、無理して働いている方がおられます。
仕事は「人生を楽しむ」ための手段
この考え方は大切だと思います。
もちろん頑張ることは、必要なことです。
逃げてばかりもしていられません。
しかし、そこまで頑張りすぎる必要もないんですよ(^^)
環境を変えて、また頑張れば良いんです(^^)
悪化すれば治療をするしか方法はありません

体の疲れが溜まってきたなと感じている段階なら、
疲れをとる手段はいろいろあります。
しかし、悪化してしまい生活に支障が出始めたら、もう治療するしかありません。
治療にはこれらの方法を用いられます。
鍼灸、マッサージ、電気、バンド。
いくつか治療方法はあるようですが、これらは全て「痛みの緩和」が目的です。
根本的に治るわけではありません。
そのため、結局は、
- 筋力を維持・上げる
- ストレッチをし、柔軟性をあげる
- 普段の姿勢を見直す
これらが必要になります。
注意ポイント
自律神経失調症のような症状の方は意外と多い
私がこれまで一緒に働いていた職員さんの中で、
この自律神経失調症のような症状に悩まれている方は、けっこういました。
もし、そうかも?と感じた方は、一度受診しても良いかと思います。
さらに詳しく
加齢に伴い体の機能は低下します

人間は加齢に伴い、嫌でも体の機能は低下します。
そのため、若い頃と同じような働き方はできなくなります。
自分の働き方を見直すことも大切になります。
他人に任せることを覚える
これまでは、一人でできていたことでも、
どうしても体がついてこないことが増えます。
そのため、他人に仕事を任せることを覚えましょう。
仕事をするうえで、責任感は必ず必要ですが・・・。
あなたがいなくても会社は回ります。
そう考えることで、少し気が楽になる方もいると思います(^^)
働き方を変える
仕事をするうえでの働き方は、正社員だけではありません。
正社員にこだわらなくても、非常勤や派遣という働き方もあります。
今は、派遣でも正社員と同じくらい給料がもらえる施設もあります。
経済的な状況、あなたの体調などと相談し、見直すことも一つだと思います。
働く部署、施設を変える
資格をとることで、相談員や管理者にあることもできます。
体力が落ち、現場がしんどいと感じるようになったら、
そういう道を考えるのも一つです。
夜勤ができなくなると、夜勤手当はでませんよね。
夜勤手当がなくなるのは、経済的に辛いのも分かります。
- 夜勤がない仕事をするか
- まだ身体に負担が少ない施設で夜勤をするか
これらを考えることもできます。 しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 この記事では、転職サイトについて書いていきたいと思います。 転職サイ ... 続きを見る
私の知り合いに、有料の夜勤専属の派遣で働いている方がいます。
その方は、月々手取り20万くらいもらっているようです(^^;)
その知り合いは、「きらケア」で仕事を探したみたいです。
「きらケア」は、時給の高い施設の募集を多く持っておられるため、
こちらを利用すると、そういった働き方も現実的になります。
転職サイトも、各会社により特徴が違うので、自分に合いそうなサイトを、
複数登録しておくと、比較することもできますよ。

転職サイトには、どんな特徴があるの」?
おわりに
この記事では、日頃「体の疲れがとれない」と感じている方にむけ書いてきました。
私も10年以上介護に携わっているので、いろいろ悩んできました。
そして、年々夜勤が辛くなってきています(^^;)
だからこそ、今の自分に合った働き方もあるのかなと思います
現在、辛い思いをして働いている方も多くおられます。
「あなた」しか守ってあげられない「あなたの体」。
自分の人生を大切にして下さいね(^^)
-

-
「私もあんな風になるの?」認知症の本人が不安な思いを告白
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ...
-

-
介護施設に潜む闇:若い芽をつむお局さまの言動6選と攻略方法
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ...
-

-
【ほんまでっかTVから学ぶ】認知症ケアに活かせる対応方法
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ...
-

-
【介護職あるある】職員(先輩)により介助の「やり方」が違う
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ...
-

-
【みんな同じ時間に介助?】排泄介助にも個別性を求めましょう!
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ...
最後まで読んで頂きありがとうございました(^^)
良い記事だなと感じて頂けましたら。
- いいね!
- シェア
お願いします♬
※TOPページから、メールアドレスを登録して頂けますと、最新記事がいち早くメールで届くようになります。