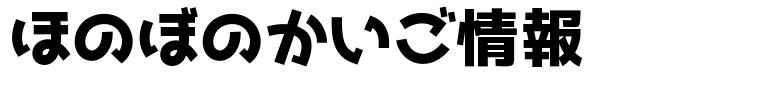投稿者のしんです。
私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。
その後かれこれ10年以上、介護現場で働いています。
2年~3年で、1つの部署を異動してきました。
特別養護老人ホーム、グループホーム、ショートステイをこれまで経験し、今に至ります。
今後のキャリアとしては、「しろくま介護ナビ」を利用して、在宅施設のサービスを経験していく予定です。
日本の介護の現状と課題を、施設介護の観点から学びたいと思っております。
-

-
しろくま介護ナビはどんなサイト?
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後かれこれ10年 ...
続きを見る
介護をするうえで、「人間関係」の悩みは、必ずつきまといます。
私は、長年、介護現場で多くの失敗をしてきました。
その経験を通して、お伝えできることがあります。
こちらの記事で少し楽になると思います(^^)
-

-
人間関係で悩まれている方へ
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後かれこれ10年 ...
続きを見る
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ... 続きを見る
この記事では、介護職のみなさんが普段からしている排泄介助について書いていこうと思います。
みなさんの施設では、個々のご利用者の排泄にまわる時間はどのように決めていますか?
現在では、個々の排泄状況に合わせて介入することが当たり前となっています。
しかし、私がこれまで経験してきた施設の中には、「排泄の時間」というものがあり、一斉に排泄に回るケアをしている場所もありました。
この記事を通して、排泄に介入する時間をどのようにチームで検討していくのかをお伝えしたいと思います。
排泄介助に慣れないよ・・・。という方はこちらの記事を参考にしてみて下さい。

排泄介助はみんながぶつかる壁
~もくじ~
【みんな同じ時間に介助?】排泄介助にも個別性を求めましょう!

ご利用者にとって「排泄介助」というものは、多くの障害があります。
誰も他人に自分の恥ずかしい部分を見せたいとは思っていません。
また、尿失禁など排泄を失敗したという事実は、「こんなことになるなんて死んだ方がマシだ」
自分自身で自分を責めたくなる気持ちもでてきます。
想像してみたら分かると思いますが、もし私たちも同じような状況になったら同じことを感じると思います。
ご利用者がこういう感情になるのは当たり前のことと言えます。
介護者もそれを念頭にケアしていく必要があります。
どういう視点でのケアが求められるのか?
それでは、どういう視点でケアしていていけば良いのかをお伝えします。
食事・排泄・入浴等、どのケアにも言えることですが、「私たちが普段している生活に近づける」といことを意識しましょう。
「私たちが普段している生活」と聞くと、疑問があるかもしれません。
- 普段、おむつを履いて生活されている方いますか?
- 普段、トイレに行かずオムツの中で用を足される方はいますか?
- ご家族全員、毎日同じタイミングでトイレに行きますか?
- 寝るときに防水シーツを布団にひいて寝ている方はいますか?
これらを質問された時、ほとんどの人が「NO!」と答えますよね。
(なぜ英語かは分かりませんが・・・。)
高齢になると、老化や病気の影響で、体の機能が低下します。
排泄で失敗することも増えてきます。
しかし、失敗が多くなってきたからといって、パットの大きさを変えたり、リハパン・オムツ等を変える。
これはご利用者からすると「不快」です。
パットが大きくなることで、ごわごわしたり、太ももにギャザーが当たったりと嘘でも気持ちが良いとは言えません。
しかし、その一方で、「排泄を失敗する」ということもご利用者からすると不快な状況です。
注意ポイント
「排泄介助に介入はしてあげたいけど、あまり介入しすぎるのも申し訳ないな」
介護者は悩むとこですよね。
ケアの質を上げるとこれまでできなかったことができる!?
排泄介助を考える際、必ず意識してほしいのは、そのご利用者の排泄リズムです。
排泄リズムが把握できたら、今までできなかったことができるようになるかもしれません。
- 排泄アイテムを変更できるかもしれません(オムツ ➡ リハビリパンツ ➡ テーナパンツ ➡ 布パンツ)。
- 防水シーツをはずしてあげられるかもしれません。
- 排泄の失敗を「0」に近づけられるかもしれません。
こういった考え方は、その人らしい生活、人間らしい生活をしていくうえで必ず必要な考え方だと思います。
排泄介助はデータをとり分析することから始まる

それでは、具体的にどのような手順で排泄介助を検討していくかをお伝えします。
step
13時間に1回排泄介助に介入する
データをとる期間を3日間などと決め、その期間内は日中・夜間帯を通して3時間おきに排泄介助に入ります。
なぜ3時間に1回なのか?
step
2尿測をして、どのくらいの量が出ていたかを確認
排尿の量をはかり、どのくらの量が出ていたのかを確認します。
測り方はいろいろあります。
私たちは、はかりを置きそこに置くことで重さを数値でだす方法を使っていました。
(汚染したパットの重さ ー 新しいパットの重さ=排尿量)
step
3トイレで排尿がでる時間を予測する
集めたデータから、なるべくパットや下着が汚れることなく、トイレで排尿がみられそうな時間を予測します。
step
4業務を調整する
「他の業務があるからそんな時間には見れないよ!」と思う方もおられると思います。
しかし、それは本当にそうなのでしょうか?
「その時間にその業務をしなければいけない」と勝手に決めつけていませんか?
介護職として忘れてはいけないこと
業務を回すことを仕事の主軸に考えてしまうと、ご利用者のケアは後回しになります。
ご利用者のケアこそが、介護職の仕事です。
ご利用者の生活の状況に合わせて、業務は変化します。
最後にみなさんにお伝えしたいこと
この記事では、みなさんが普段からしている排泄介助の考え方について書いてきました。
いかがだったでしょうか?
排泄介助は、1日の中で何度も介入する介助内容になります。
ご利用者からすると、1日に何度も他人に自分の恥ずかしい部分を見せる時間になります。
このことは、介護職をされている方なら、もちろんご存じのことだとは思います。
しかし、毎日常にこのことを意識しながら働くことは難しいですよね。
気持ちはよく分かります。
しかし、ケアを考えるときは必ず意識するようにして下さい。
ご利用者は十人十色です。
食事を食べたい時間、トイレに行く時間、日々の過ごし方・・・。
全員一緒はありえません。
「その人らしい生活」を目指す介護には、日々のケアの考え方が大切になります(^^)/

- TOPページから、メールアドレスを登録して頂けますと、最新記事がいち早くメールで届くようになります❕