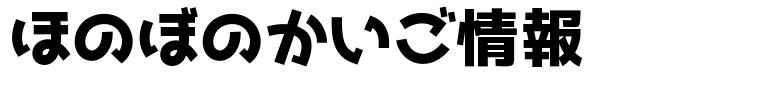投稿者のしんです。
私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。
その後かれこれ10年以上、介護現場で働いています。
2年~3年で、1つの部署を異動してきました。
特別養護老人ホーム、グループホーム、ショートステイをこれまで経験し、今に至ります。
今後のキャリアとしては、「しろくま介護ナビ」を利用して、在宅施設のサービスを経験していく予定です。
日本の介護の現状と課題を、施設介護の観点から学びたいと思っております。
-

-
しろくま介護ナビはどんなサイト?
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後かれこれ10年 ...
続きを見る
介護をするうえで、「人間関係」の悩みは、必ずつきまといます。
私は、長年、介護現場で多くの失敗をしてきました。
その経験を通して、お伝えできることがあります。
こちらの記事で少し楽になると思います(^^)
-

-
人間関係で悩まれている方へ
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後かれこれ10年 ...
続きを見る
新人指導のシステムには、プリセプター制度、OJT(職場内訓練)などいくつか種類があります。
それぞれの施設でどの指導システムをとられているのかで、ついてもらう期間は変わってくる印象があります。
OJT(職場内訓練)は数か月。
プリセプター制度は1年。
私はこれまでの経験から、こういう印象をうけています。
聞いた話によると、入社して1週間で独り立ちする施設もあるようです。
常に指導担当と一緒の同じ勤務をこなすよう勤務を調整してくれる施設もあります。
その一方で、職員不足により、日により指導者が変わるという施設もあります。
そこで出てくる問題。
職員(先輩)により介助のやり方が違う
これで悩まれている職員の方も多いと思いますので、今回はこの内容について書いていきます。
~もくじ~
【介護職あるある】職員(先輩)により介助の「やり方」が違う

新人の方や、中途採用の方でも、介護職未経験の方は介護について右も左も分からないですよね。
ましてや、介助なんて・・・。
- どうして先輩ごとに介助の方法が違うの?
- 指導についてもらう職員と同じやり方でしたら良いの?
- 結局何が正解なの?
こういう悩みは、ほとんどの方が経験することだと思います。
ただでさえ慣れない職場で気をつかうのに、介助のたびに指導職員の顔色を伺う。
疲れますよね(・・;)
では、どうして先輩により介助のやり方が違うのでしょうか?
どうして先輩により介助のやり方が違うの?
「先輩のやり方が違う」この理由で考えられるのは、3つのことが理由としてあるのかなと思います。
何人かの先輩が正しいやり方を知らない
これはそのユニットのリーダーの責任です。
ユニットの中で情報共有がうまくいっていない、または職員の育成ができていないか。
どちらかが問題かと思います。
先輩が実際しているやり方を教えようとしている
これは、「業務を優先」しているか「ご利用者を優先」しているのかのどちらかのケースに分かれます。
もちろん本来なら、最初のうちは「ご利用者を優先したケア」を教えるのが当たり前です。
しかし、職員の中には業務を優先した方法を教える方もいます。
- ご利用者を大切にした介助の指導の方法を知らない
- とにかく早く動ける職員に育てたいと思っている 等
これらの理由があるかと思います。
全員が同じやり方をしていると体を痛める職員が出てくる
全ての介助に言えることですが、1つのやり方を全員が同じようにしていると、体を痛める職員がでてきます。
働いている職員は、それぞれ体型、筋肉量、身長等が違います。
ご利用者を抱える動作1つにしても、ある職員にとってはちょうどの位置かもしれません。
しかし、その職員より身長の高い職員は、常に中途半端に腰を曲げた状態になります。
自分の体を痛めないためにも、自分の体に合った介助方法を見つける必要があります。
それも、未経験の方が「職員によってやり方が違う」と思う1つかもしれませんね。
指導が上手い職員の特徴とは?
私が個人的に指導が上手いと思う職員の特徴は、指導される側にとって介助しやすい方法で教えることができる方です。
介護における身体介助は、介護者の体を痛める原因になります。
自分に合った介助方法をしないと、すぐに痛めてしまいます。
そのため、ご利用者の状態と指導される側の体型、筋肉量、身長等を考慮して、その職員に合った介助方法を一緒に考えてくれる。
このような指導者は素敵だと思います。
介助方法をどのように覚えていけば良いのか?

先輩職員により介助のやり方が違うので、どの方法で覚えていいのか分からない。
そう感じている職員の方は、下記の3つの点を意識してみて下さい。
- 「してはいけないポイント」「ユニット内で統一している内容(決まり事)」を押さえる
- ご利用者が感じる「不快」を少しでも少なくする
- 自分の体型に似た職員に相談する
この3つを意識して介助を覚えれば、介護技術はうまくなると思います。
「してはいけないポイント」「ユニット内で統一している内容(決まり事)」を押さえる
「(ご利用者に)こうしてあげて欲しい」この思いは、職員によりさまざまです。
職員によっては、自分がこだわっている思いも指導の際に伝える方がいます。
その熱い気持ちはとてもすばらしいことだとは思いますが、指導される側から最初は覚えきれないと思います。
そのため、してはいけないポイントをまずは押さえるようにしましょう。
- こういう誘い方をすると、嫌がられ介助に入れなくなる。
- これを置いておかないと、転倒される危険がある。
- この位置に物を置いておかないと、混乱される。 等
まずは、こういった事故につながる危険があることを重点的に覚えましょう。
また、「この方は食事を介助する前に水分をすすめる」や「トイレ誘導のたびに陰部洗浄をする」等。
ユニットの中でケアを統一しようと、決められている事があると思います。
それらは確実に覚えておきましょう。

ご利用者が感じる「不快」を少しでも少なくする
先の内容で、それぞれの職員がこだわる部分は違うということをお伝えしました。
少し介助に余裕が出てくれば、それぞれの職員のこだわりも大切にしながら、自分なりにご利用者が感じるであろう「不快」を少しでも少なくなる方法を考えていきましょう。
介護職として、「もっと〇〇してあげたい」「〇〇してあげたらどうだろう?」という視点は、必ず必要になります。

自分の体型に似た職員に相談する
基本的にご利用者の介助は、ベテラン・新人関係なく誰もが同じ質でできる方法を考えなければいけません。
しかし、どうしても体格の差で「難しい」や「体が痛い」ということがあります。
その時は、自分と似た体格の職員に相談するのもおすすめです。
その方がどのような点に注意し介助をしているのかを知ることで、真似しやすくなります。
ポイント
あなたの指導者が、こう助言をくれる指導者ならラッキーです。
ちゃんと指導される側の立場のことを考えてくれる方だと思います。
慣れないうちは「とりあえず聞いておく」
職員間でのやり方の違いで、今まさに悩まれている方にお伝えしたいこと。
それは、「とりあえず聞いておく」ということです。
今すぐ全員同じやり方で教えてもらえるようになったり、今すぐ同じ職員に指導してもらうように勤務を調整するのは難しいと思います。
そのため、最初は大変だとは思いますが、今はとりあえずみんなの言うことを聞いておきましょう。
職員Aさんのやり方を、職員Bさんの前ですると注意されるかもしれません。
その時は、とりあえずその時はBさんの方法でしましょう。
「Aさんは、このやり方をされていましたから!」と強く言ってしまうと、Bさんとの関係が悪くなる可能性があるので。
そして、後日、指導担当の方に相談しましょう。
職員によりやり方が違うから困っていることは、必ず伝えて下さい。
知っていてもらうのと、知ってもらっていないでは違います。
もしかしたら、配慮してもらえるかもしれないですよね。
最後にみなさんにお伝えしたいこと
この記事では、介護未経験の方が必ず感じる「先輩により介助のやり方が違う」ということについて書いてきました。
いかがだったでしょうか?
この悩みに関しては、おそらく全員が感じる内容です。
全員の介助方法が同じの方が良い点もあると思います。
- 説明する時に全職員が同じ内容を伝えることができる
- 一定の質のサービスが提供できる 等
しかし、記事の中で説明した通り、デメリットがあることも知っておいて下さい。
「してはいけないポイント」や「統一すべき内容」はきちんと決めておく必要はありますし、それに関しては全員が日頃からしておかなくてはいけません。
未経験のうちは、右も左も分からないと思うので、まずはこの2つの内容を覚えることから始めても良いと思います。
ポイント
その時は指導担当者に質問して確認することが良いと思います(^^)/

- TOPページから、メールアドレスを登録して頂けますと、最新記事がいち早くメールで届くようになります❕