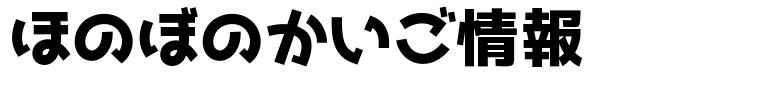投稿者のしんです。
私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。
その後かれこれ10年以上、介護現場で働いています。
2年~3年で、1つの部署を異動してきました。
特別養護老人ホーム、グループホーム、ショートステイをこれまで経験し、今に至ります。
今後のキャリアとしては、「しろくま介護ナビ」を利用して、在宅施設のサービスを経験していく予定です。
日本の介護の現状と課題を、施設介護の観点から学びたいと思っております。
-

-
しろくま介護ナビはどんなサイト?
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後かれこれ10年 ...
続きを見る
介護をするうえで、「人間関係」の悩みは、必ずつきまといます。
私は、長年、介護現場で多くの失敗をしてきました。
その経験を通して、お伝えできることがあります。
こちらの記事で少し楽になると思います(^^)
-

-
人間関係で悩まれている方へ
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後かれこれ10年 ...
続きを見る
みなさんは、後輩の指導に頭を悩ませたことはないですか?
人に「指導」することは、すごく難しいですよね。

- なんで同じミスを繰り返すの?
- もうちょっと自分で考えてみてよ!
- どうしたら分かってもらえるんだろう・・。
指導に関するこれらの苦悩は、誰もが経験しているかと思います。
この記事では、これまでの私の経験を通して、
- 私自身がこの時がすごく勉強になった
- こういう教え方をされたから、頑張れた
これらをお伝えしていきたいと思います。
~もくじ~
【介護職の指導】人が成長する時は、必ず「環境」が影響します。

人はどんな時に成長を感じるのでしょう?
大きく分けると、2つの場面で感じることができると思います。
- 自分自身を振り返った時
- 周りからの評価
主にこれら2つの場面で感じると思います。
- できなかったことが、できるようになった!
- 新しいスキルや資格を習得した!
- 周りからの良い評価をしてもらえた!

「成長」というものは、自分の頑張りに後からついてくるものということです。
「成長」を実感できれば、より成長する
新しく何かを始めたときは、右も左もわからない状態だと思います。
その状態において、できなかったことができるようになるということは、1つの成長です。
よく指導をする時、「褒めて伸ばす」方法が良いと聞いたことありませんか?
その指導が良いか、悪いかは置いといて、
本人の成長を本人に伝えてあげる
このことは、とても大切です。
ポイント
【大切な考え方】自分で自分の成長を実感できるようにする
読んでくれているみなさんの中に、
毎日、仕事中に「成長のため」と意識している人はいますか?
そんな方はすごく少ないのではないでしょうか?
それはなぜか?
それは、実際の指導を行っている現場において、
「成長」という言葉が、すごくあいまいな使い方をされているのが、
原因の1つだと考えられます。
指導者が「これは、あなたの成長につながるから」と伝えても、
後輩は「成長」という言葉の響きだけで「はい」と言葉を返すでしょう。
- 何に対しての成長なの?
- なにができるようになるの?
- どうなれば良いの?
これらが明確に理解できないから、何度同じことを言っても同じ失敗につながるんです。
指導の際に重要なポイント
- 対象者の明確な目標を設定すること
- その目標を対象者と共有すること
この2点は、指導する際に、対象者への言い方等と同じくらいに重要です。
指導する際の目標設定ついては、こちらの記事で詳しく書いています。
参考になると思いますので、是非みてみて下さい。
【参考】新人指導で意識すべき3つのポイント
人はどんな時に「成長」するのか?
人が成長する時は、どんな時なのでしょう?
- 何か壁にぶつかった時
- 悩みやストレスを感じ、改善策を探す時
- 新たな資格・スキルを身につけたい時
- 他人に期待されている時
人は、自分がこれらに当てはまった時、1つの課題に対して、
乗り越えようします。
自分から、自分の目標のために「よし!成長するぞ!」と前向きに取り組める時もあります。
しかし、壁にぶつかったり、辛い時に、
「今の現状をとにかくなんとかしたい」と必死にもがくこともあります。
もちろん、その時は「成長」というプラスのイメージはなく、その時は、
ただ、その状況を乗り越えることだけを考えます。
そして、しばらく時間が経った後、自分自身を振り返り、
「成長」を感じます。
伝わる指導をしたいなら「環境」を意識せよ

指導する時には、介護という形ないものを、伝わる形にして、言葉で伝えないといけません。
そのため指導者の表現方法や、後輩にとって覚えやすい方法で指導することが求められます。
しかし、それと同じくらい重要になるポイントがあります。
それは、その対象者(後輩)が「置かれている環境」です。
- 分かりやすく例えを使い説明します!
- 分かりやすく例えを使い説明します!
具体例
実家にいると親のありがたみは、当たり前となり分かりません。
しかし、独り暮らしをした途端に、親のありがたみが分かるようになります。
1人で食事・掃除・洗濯。 今までどれだけ助けられていたのか。
これと同じです。
親のありがたみを指導しようとした場合
実家で時間をかけ何を言っても、現状が満足できるものなら、
おそらく流されるか、3日坊主になりそうです。
しかし、独り暮らししないといけない環境になれば、嫌でも分かります。
「自分しか家事をする人がいない」状況であれば、責任感が出ますよね。
独り暮らしがすぐには無理なら、
同じように責任感が持てるような工夫を考えることもできます。
実家にいても、今日から1週間私は何もしません!と宣言する 等
大切なポイント
- 対象者が「本当に変わらなければならない」と自分自身で感じること。
これこそが、指導する際にとても大切なポイントになります。
この環境設定を行う際には、必ず注意しないといけないことがあります。
それは、必ず対象者と話し合って決めて下さい。
上司が勝手にそういう環境に置いてしまうと、職権乱用・パワハラに捉えられ、
逆に不信感につながります。
【経験談】他職員の意見をきく重要性
私が過去、グループホームのオープニングスタッフとして、
働いていた時の出来事です。
そのグループホームは、9名のご利用者が入居されており、
私は、9名のご利用者のケアプランを作成していました。
全ご利用者が新規入所なので、毎月平均3人のケアプランを見直しをしていました。