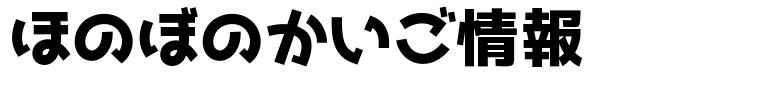投稿者のしんです。
私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。
その後かれこれ10年以上、介護現場で働いています。
2年~3年で、1つの部署を異動してきました。
特別養護老人ホーム、グループホーム、ショートステイをこれまで経験し、今に至ります。
今後のキャリアとしては、「しろくま介護ナビ」を利用して、在宅施設のサービスを経験していく予定です。
日本の介護の現状と課題を、施設介護の観点から学びたいと思っております。
登録者の立場に立ってもらえるサイトなので、信頼しています。
この記事では、介護職の「やりがい」について書いていきたいと思います。
先日このようなツイートをしました。
施設の利用者からの発言。
良く聞く言葉。
☑️「はよ死にたい」聞いたことがない言葉
☑️「もっと長生きしたい」介護のやりがいは、人それぞですが、結局この言葉がポイントになってる気がします🤔
— あだっさん (@RO1MWPq0wPb2sga) June 20, 2020
これについて、書いていきたいと思います。
~もくじ~
【介護職のやりがい】ご利用者の声「はよ死にたいわ」

私は、これまで介護の仕事をしてきて、ふと感じたことがあります。

- はよ死にたいわ
- 長生きばっかりするもんじゃないわ
ご利用者から、この言葉はよく聞きます。
しかし

- 長生きは良いこと!
- もっと長生きしたいなー
という言葉は聞いたことないんです。
世間的に「長生きすることは、良いこと!」とされていませんか?

この言葉には、いろいろな思いがあると思います。
加齢に伴う体の変化
私たちは、いつまでも若いままでいたいですよね。
しかし、そういうわけにはいきません。
体は正直ですよね(^^;)
必ず訪れる身体の機能低下
加齢と共に、身体の機能は低下すると言われています。
- 呼吸器系・・・努力肺活量の低下
- 心血管系・・・心臓の働きが悪くなる
- 消化器系・・・嚥下障害など
- 腎泌尿器系・・排尿障害など
- 骨運動系・・・骨粗しょう症など
- 感覚系・・・視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚

人間は30歳をピークに、その後、緩やかに低下していくと言われています。
【精神心理面】全てが低下するわけではない

精神心理は、「知能面」と「精神面」に分けることができます。
知能面は全てが低下するわけではない
知能面は2つにわけることができます。
「流動性知能」
- 推論する力
- 思考力
- 暗記力
- 計算力 等
※加齢による影響をうける
「結晶性知能」
- 料理などの日常の習慣
- 長年にわたる趣味の手順や方法 等
※加齢による低下が少ない
【精神面】加齢で変わるのは自分だけではない
精神面は、加齢の影響で低下しにくいと言われてます。
年齢を重ねるということは、周りの環境も変わっていきます。
そのため、精神面で一番深く関係していくのは、「喪失体験」と言われています。
- 配偶者・兄弟・友人との死別
- 定年退職による社会的立場の喪失
- 動かなくなっていく体
- 嫌でも受け入れないといけない「他人からのお世話」
そして、それらによる、人生の生きがいの喪失。
生きるのが嫌になり自殺を選択される方もいます。

これは、警視庁から出ている、令和元年の自殺者の統計データになります。
上の表でもあるように、「健康上の問題」が高齢者の自殺の7割を占めています。
もちろん病気になることで、今後の人生を生きていくことが辛くなられたのかと思います・・。
「はよ死にたいわ」この訴えの真意は?
正直、確かな理由は、私にも分かりません。
しかし、年をとると身体の機能が落ち、仲が良かった人も徐々にいなくなる。
自分自身も手伝ってもらわないと、一人で生活することすらできなくなる。
情けない・・・。
寂しい・・・。
生きていても良いことなんてない・・・。
「生きがいもなく何の目的もなく生かされている」
こういった思いが背景にあるのではないでしょうか。
介護職のやりがいのある仕事
介護職は、とてもやりがいのある仕事だと思っています。
誰かの、社会の役に立てる仕事で、「人の最期の人生に関わる」
本当に誇りが持てる仕事です。
これから介護の仕事をしよう!と思った方も、こういう思いの方は多いようです。

【参考】平成28年介護労働実態調査
- 高齢者が好きなら。
- 人をお世話することが好きなら。
- 誰かの役に立てるような仕事をしたいなら。
ぜひ、介護をしてほしいと心から思います。
介護施設の現実
働き始めて感じた方も多いのではないでしょうか?
現実と理想は違う!!
私も感じました。
介護について何もしらない時は、講義でうける「介護の理想」がそのまま、施設で行われていると思っていました。
しかし、いざ働きはじめたら、違いました。
毎日時間に追われ、バタバタと。
どうやって業務をまわそう・・・。
職員の中には、仕事しにくい人がいる・・。
そしていつのまにか、「業務を上手く回す=良い職員」
・あの子は仕事が遅い
・あの人は仕事ができない
これについては、一概には否定しません。
しかし・・・。
そももそも仕事の趣旨がずれていますよね?
話題のツイートをご紹介
以前、Twitterで話題になったものがありました。
それがこちらです👇
『次は天丼くいたい!』『天丼はないっす!ラーメンなら作れます』『じゃあ、ラーメン!』えっと、夜中3時半。
10日前まで半年間、ずっと病院でペースト食だった反動なのか、ほんっとに美味しいみたい。食べることは生きることだと教えてくださってる。 pic.twitter.com/StAUphETK5— 菅原健介@ぐるんとびー (@KensukeGru) May 20, 2020
もちろんですが、賛否両論です。
- これが介護の理想だ!
- ペースト食の人に常食は危険すぎる!
などなど。
双方の気持ちはよくわかります。
みなさんが同じ立場なら、どうしてました?
私の意見は、「その場では提供できない」です。
これを実行した方は、介護職としてベテランの方だと思います。
じゃあこれを入社して半年の子が、同じことをして事故をおこしたら・・・?

本人の思いとそれに伴うリスク
本人の思いにできるだけ実現する。
「介護は、そもそもこういうものだ」
悲しいことですが、実際現場でここまでできる施設は少ないと思います。
「介護はそういうもの」と私も思います。
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 この記事では、レビー小体型認知症について書いていきます。   ... 続きを見る
介護者の立場としてはね。
こちらの記事でも書きましたが、介護者に人の人生を決める権利はありません。

介護者に人の人生を決める権利はない
その方の人生を決めることができるのは、本人とご家族だけです。
この件は、人の人生を決めてしまう可能性が高いと思います。
その人のため? 介護者側の自己満足?
私自身も今でも悩みながら働いていることです。
それ、あなたの自己満足じゃないですか?
介護者側が勝手に「〇〇をしてあげよう!」と思っているだけで、本人は本当にそれを望んでいるんでしょうか?
良かれと思ってしていることが、実は間違っている
こんなことも、よくあります。
チームでご利用者の希望を実現しよう!
このツイートを例にします。
ご利用者から「ラーメンが食べたい」と希望があったら、必ずチームで話し合いましょう。
ペースト食の方に常食を食べてもらうメリット・デメリットを。
※医療職からは猛反発をくらいます(笑)
その後、話し合いで出た意見を、必ずご家族に相談しましょう。
私の実際の経験談(ご家族との話し合い)をこちらの記事に書いています。
もし、ご家族から、デメリットを理解した上で「好きな物を食べさせてほしい」と希望があれば・・・。
今度はチームでどうやったら常食で食べてもらうことができるのか?
を話し合いましょう!
心配しなくても、大丈夫です。
医療職の目は冷たいです(笑)
「ご家族からも希望があった」と、前向きに協力してもらえるように努力しましょう!
さいごに
年齢を重ねると、どうしても自分の状況や、周囲の状況が変わります。
それにより「もう生きてても仕方がない」、「寂しい」
こう気持ちになると思います。
でも、だからこそ私たち介護職がいるんだと思います。
私たちの仕事は、身体介助だけではないです。
それ以上に大切なことがあります。
また、介護職一人でできることなんて、たかが知れています。
チームみんなでやらないと、意味がありません。
そういうチーム作りを日頃からしていきたいですね(^^)
最後まで読んで頂きありがとうございました(^^)
良い記事だなと感じて頂けましたら。
- いいね!
- シェア
お願いします♬
※TOPページから、メールアドレスを登録して頂けますと、最新記事がいち早くメールで届くようになります。