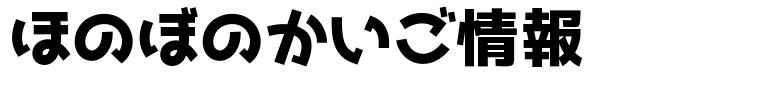投稿者のしんです。
この記事では、レビー小体型認知症について書いていきます。
認知症の中でも、罹患されている方の割合はとても少ないです。
それだけに、施設でどう対応していくのか。
どうしていいのか分からなくなる職員も多いです。
私も介護歴は10年以上ですが、これまで2人しか会ったことありません。
こういう対応をするべきだ!というサイトがあります。
はっきり言います。
教科書通りの理想通りの対応は、まずできません。
何も知らなければ、確実にその人の人生が変わるレベルの事故が起きます。
私の経験を通して、レビー小体型認知症の対応について伝えていきます。
~もくじ~
【私の経験上一番悩んだ介護】レビー小体型認知症の対応の難しさ

最初に、レビー小体型認知症とはどんな病気なのか?
簡単に説明します。
レビー小体型認知症とは?
レビー小体型認知症は「3大認知症」と言われています。
罹患者は「アルツハイマー型」「脳血管性」に次いで3番目になります。
【参考】最新調査結果 厚生労働省:認知症施策の相互的な推進について

3番目といっても、全体の割合では罹患者は非常に少ないです。
実際にケアを経験したことがある人も少ないのではないでしょうか?
主な症状は?
主な症状は下記です。
- 認知機能障害
- 幻視
- レム睡眠期行動異常症
- 自律神経症状
- うつ状態
認知機能障害
一般的に認知症は、記憶力などの認知機能が次第に低下する症状が現れます。
しかし、レビー小体型では、認知機能の調子が良いときと悪いときが交互にやってきます。
そのため、調子が良いときの状態だけを見ると、認知症を発症していると判断できないことも多いです。
幻視
実際にはその場にいない人や小動物などが、本人にはありありと見えるようになります。
「虫が床を動いている」や「子どもが廊下で遊んでいる」など、話す内容は具体的なことが多いです。
パーキンソン症状
- 手足が震える
- 筋肉のこわばり
- 動作がゆっくりになる
- 表情が乏しくなる
- 前かがみ・小刻み・すくみ足歩行
これらがみられます。
レム睡眠期行動異常症
人は睡眠中、ノンレム睡眠(深い眠り)と、レム睡眠(眠りが浅い)交互に繰り返しています。
レム睡眠時に奇声を上げる、暴れるなどの異常行動が現れることがあります。
自律神経症状
自律神経症として現れるのは以下のような症状です。
- 睡眠時の寝汗の増加、多汗
- 立ちくらみ
- 頻尿または尿失禁
- 便秘
- 動悸
- 体のだるさ
うつ状態
レビー小体型認知症の発症後、初期の段階からみられることが多いです。
認知症ではなく「うつ病」と間違われることも少なくありません。
気分が沈みがちになって悲観的になり、生活上のあらゆることに対して意欲が失われる症状です。
薬剤過敏性
- 様々な副作用が出る
- 通常の量で症状が悪化
- 薬が効き過ぎる 等
処方された薬で症状を悪化させたり、新たな問題を発生させることがあります。
市販の風邪薬や胃腸薬で具合が悪くなることもある。
処方は、専門家でも非常に難しい。
医師には慎重な姿勢が求められる。
【参考】みんなの介護:レビー小体型認知症とは?
レビー小体型認知症の症状をまとめると、下図のような感じです。

私はこれまで、2人のレビー小体型認知症の方の人生に関わりました。
1人はグループホームで、1人は特養です。
その1つの事例をご紹介します。
実際に経験した難しさ
70代 女性の方。レビー小体型認知症に罹患。

入所に至った経緯
その方はこれまで、ショートステイ等いくつかの施設を利用はされてきました。
その全ての施設で、「うちでは看れない」という理由で、入所を断られていたようです。
そんな中、私が働くグループホームに入所となります。
入所当初
1日の大半をリビングで過ごされていました。
休憩で横になって頂いても、すぐにリビングに起きてこられていました。
入所当初は、パーキンソン症状の影響で、歩行が不安定なため、転倒リスクを懸念していました。
トイレに行かれる回数も多かったです。基本的に30分に1回位のペース。
多い時は、トイレが終わった瞬間に「トイレ行く」と言われます。
職員の負担(入所当初)
正直、大変でした。
仕事としての業務をしながら、その方の対応をしていたので。
グループホームなので、他に入所している方も全員認知症を患っておられます。
それぞれのご利用者に精神状態が安定しない状況があります。
しかし、その方にどうしてもケアが集中してしまうのが現状でした。
他のご利用者のケアに十分に時間を使うことができませんでした。
本人の負担(入所当初)
本人もトイレの数が多くなると、体をよく動かすので、血圧が上昇するのかソワソワされていました。
その焦燥感を伴う訴えで、より歩行が不安定になります。
本人も精神的にしんどかったと思います。
ご家族の協力
ご家族は、本当に良い方で介護職への理解もありました。
今から思っても感謝しかありません。
ある日、ご家族から提案がありました。
提案の内容は、「私が毎日来て、親をみさせてほしいんですが・・・」というものです。
普通なら毎日介護しに来ると言われたら、断ります。
- (ご家族)施設から出されると行く場所がない
- (介護職)他のご利用者の対応もしっかりしていきたい
これらの意見で、心残りはありながら、提案を了承しました。
その後、ご家族は休むことなく毎日施設にこられました。
夕食前~就寝前まで、本人に付き添ってくれるようになりました。
施設のご利用者全員がソワソワされる時間です。
しかし
認知症の症状は進行します。
認知症が進行したことで、生活が激変
歩行レベル
1歩あるけば転倒する程まで低下。
本人の精神状態
- より周囲の環境に敏感になる
- 本人の中でご家族や職員への依存心が高くなる
という状態になっていきました。
「先生、私どうしたら良いの?」という訴え。
短い間隔で10秒に1回、長い間隔でも20秒に1回。
もちろん、他の認知症状も進行しています。
職員が疲れていたり、忙しい時。
本人の声に返答できなかったり、流してしまう時もありました。
そうすると、「聞こえてないのかな?」といった感じで、椅子から立ち上がり職員の側に行こうとされました。
ふらふらな足どりで・・・。
もちろん分かってますし、常に毎日していました。
ただね、介護者の精神状態がもたないくらい、しんどかったです。
- ご本人
- 毎日みてくれているご家族
- 対応している職員
全員がとてもしんどいと感じる状況に。
服薬調整を行うため精神病院へ入院
入所中、服薬調整を行うため、精神病院へ入院されたことも2度あります。
ご家族、職員、医師の間で、その方の今後について話し合いをしていました。
- 精神的安定のために精神薬を検討?
- ADL(歩行や嚥下)を維持したいなら、精神薬をそこまで使えない・・・。
しかし、ここで問題になったのが、「薬剤過敏性」というもの。
認知症の中でも、レビー小体型の方にのみみられる症状です。
どちらかのデメリットに対応すると、どちらかのデメリットがでます。
しかも、事故が起きるレベルで。
服薬調整の入院を終えた後の施設生活
内服薬の状況を、施設で観察している間。
転倒、骨折、喉つめ、子宮筋腫、てんかん発作等、さまざまなことがありました。
私は、ケアプランを作成していたこともあり、管理者と一緒に最終的に下の表をご家族に説明しました。
|
精神薬 〇 |
精神薬 ✕ |
|
|
精神面 |
安定 |
不安定 |
|
ADL面 |
低下 |
維持しやすい |
|
今後の予想(デメリット) |
事故が起こる可能性高 |
他ご利用者に迷惑がかかる |
|
選択肢 |
施設の利用継続 |
退所 |
ご家族はすごく悩まれました。
ご家族間で会議をして、悩まれました。
ご家族の最終判断は、「健康でいてほしい」でした。
そのため、施設を退所されることになりました。
私たちは毎日、「その方にとって何が一番良い生活なのか」考えていました。
それだけに、ご家族の判断は、なんとも言えない気持ちになりました。
介護職に人の人生を決める権利はない
施設で生活されている時、介護職である私たちは、本当に一生懸命考えていました。
- 「どうしたら落ち着いてもらえるのか?」
- 「どうしてあげるのが、本人にとって良いのか?」
- 「職員全員で、何を目的にケアをしていけば、良いのか?」
私たちは、施設の中でご利用者にどういう生活を送ってもらうのかを考える仕事です。
全てのケア、全ての選択にデメリットが存在します。
それらを把握し、ご家族と一緒にその方の人生を考える。
この経験を通して私が感じたこと
私たち介護職の仕事は、「専門的な知識や技術をどのように人の人生に役立てるのか」を考える仕事であって、人の人生を決めるものではない
さいごに
この記事の事例は、私の介護観を大きく変えた経験になります。
正直、これまで机上で「ご家族との連携が必要」等と勉強していました。
分かっているようで、分かっていなかったのかなと感じています。
その症状が全て出現するレビー小体型認知症。
アルツハイマー型認知症と比較しても、特に医療職との連携も必要になります。
ご家族とも、メリット・デメリットをしっかり説明することで、きちんと理解してもらえる関係性を築く。
これがいかに大切なことか。
介護職・介護福祉士の仕事とは何なのか?
深く考えさせられる経験になりました。