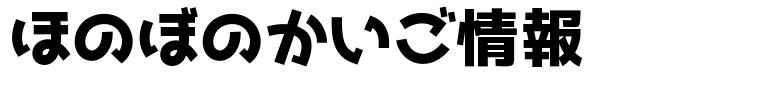投稿者のしんです。
この記事では、「認知症の暴言・暴力行為」について書いていきたいと思います。
高齢者への虐待は、しばしばニュースに上がります。
また、社会的弱者とされる高齢者には、2006年4月1日に「高齢者虐待防止法」が制定されました。
この法律により、社会で高齢者は守っていくべきだ!
という考え方が広まりました。
しかし、その反面
介護に携わる人が暴力等をうけることも、少なくありません。
それが原因で、介護が怖くなり仕事をやめたり、虐待につながったりしています。
認知症だから。
全てが許されるのはおかしいと思います。
この記事では、そういったことを踏まえどうやって介護していけばいいのかをお伝えします。
~もくじ~
【我慢しないといけないの?】認知症の暴言・暴力行為

まず前提ですが、暴力等の行為を行動分析します。
「高齢者の暴言・暴力行為」は、その人の感情表現の1つです。
もちろん簡単に許せることではないと思っています。
しかし、今ここでは、良い悪いは一旦置いておいて下さい。
どういうことか説明します。
「暴言・暴力」は感情表現の1つ
現在の65歳以上の方は、戦後貧しい時代を生き抜いてこられた方々です。
不況の時代から経済発展に貢献されてきました。
「男は仕事、女は家事」という考え方で、亭主関白な家庭が多かったのも事実です。
- 男性は、仕事一筋。
- 女性は、子どもの世話をほとんど一人で。
その当時は、子どもの数は平均2人~3人です。
時代背景から推測する性格
これらの時代を生き抜いてきた方々の特徴。
「我慢」「忍耐」「仕事一筋」「頑固」があげられます。
現在に比べると、育児や仕事において手を上げることも珍しいことではありませんでした。
これらを考えると、今より「手をあげる」ことが許されていた時代の方々です。
【認知症】症状の影響はある
年々、認知症を患っている方が多くなってきています。

上の表をみて下さい。
この表は、認知症高齢者の推移を表したものになります。
今後も大幅に認知症高齢者の人数が増加する傾向にあります。
認知症の症状が進行すると?
進行することで、さまざまな影響がでます。
- 理性の制御が難しくなる
- 自分の意志を他人に伝えられなくなる
- 妄想症状が出現
- 幻覚症状が出現(レビー小体型)
- 精神障害が合併
これらが原因とし、暴力等につながることもあります。
とはいえ
介護者に対しての暴力等が許容されるのも、おかしいと思います。
実際、それで苦しんでいる介護者も多くいます。
「訴えることで司法(法律)で裁いてもらう」
これらは可能なのでしょうか?
【我慢の限界】訴えることはできる?

結論からお伝えします。
「訴えることはできますが、認められることが少ない」
これが、現実だと思います。
理由は、認知症高齢者を「心神喪失者」とされる可能性が高いからです。
本人の認知レベルで、減刑か無罪放免になることが多いみたいです。
では
老人ホームなどに入居している認知症のご利用者間でトラブルがあった場合。
その責任は老人ホームを運営する介護事業者が負うことになるのか?
介護事業者は入居者に対しての安全配慮義務があります。
安全配慮義務違反としても賠償責任を問われる可能性はあります。
詳しいことが知りたい方は、こちらのサイトをご覧ください。
さらに詳しく
認知症患者の暴力について:弁護士の選び方 弁護士がおすすめする法律事務所
暴力等に我慢ができない時は、司法(法律)の力を借りることはできます。
しかし
ここまで読まれた方の中で、暴力を受けたい人なんていないですよね。
暴力等をどのように受けないようにするか。
考え方・対応の仕方をお伝えしていきたいと思います。
認知症の理解は必須
先にも説明はしましたが、暴力等の行為には、認知症の進行も影響します。
認知症の種類により、出現する症状は異なります。
認知症の正しい知識は必須といえます。
また、「高次脳機能障害」という病気はご存じでしょうか?
この病気は「怒りの沸点が低く、その怒りが持続する」という特徴があります。
合わせて押さえておくことをおすすめします。
さらに詳しく
高次機能障害について:All About オールアバウト健康・医療
原因分析をしよう!
正しい知識をある程度理解できたら、まずはその知識をもとに原因分析をしましょう。
なぜ原因分析をするのか?
それは・・・。
- 暴力等をなくすことができる
- 暴力等はなくせない
これを見極めるためです。
介護者の接し方が、相手に失礼にあたり、暴力につながることはあります。
勘違いはしないで下さい。
暴力等の行為をした人だけ責めるのは間違っています。
それぞれに合った対応を!
基本的に対応方法は、下記の2つです。
- 非薬物療法
- 薬物療法
この2つは、それぞれの原因に合わせて使います。
➀ 非薬物療法を用いた対応を考える
- 職員の不適切なケア
- 周りの環境因子
職員の接遇などを含めて、相手に失礼になる行動をして相手を怒らせた場合。 しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ... 続きを見る
暴力等の行動を起こすのも間違っていますが、それ以前に職員のケアを見直す必要があります。
相手を怒らせた時点で、介護者のミスです(知識・技術不足)。

伝え方を重要性
怒らせてしまって、どうしようもない時は。
- きちんと謝罪し、相手の話をきく
- 少し時間や距離を置く
- 対応する介護者を変える
この3つのことを試してみて下さい。
「相手が感情的になっている時は、こっちの理屈は通らない」
これは覚えておいて損はないと思います。
その他にも、「周りがうるさい」「嫌いな人がいる」等、周りの環境が原因している場合もあります。
暴力等の行動があった場合は、まずは非薬物療法を考えて下さい。
➁ 薬物療法を用いた対応を考える
本人自身の病気の進行は、正直どうすることもできません。
しっかりとチームで話し合い、本当にこれが原因と考えるなら、医師や看護師に相談しましょう。
「本人も自分の気持ちが伝えられず、ずっと悩んでおられる」
伝えられないもどかしさ・イライラが暴力行為を引き起こしてしまう
本人にとっては、今一番精神的に辛い時期。
こういう考え方もできます。
薬物療法の副作用
薬物療法を行う時は、必ず「副作用」を確認しておきましょう。
同じ薬でも、「合う人」「合わない人」がいます。
その副作用により、嘔気や食欲不振・倦怠感などの症状がでる場合があります。
必ず医師に確認しておき、服用を始めた日から本人の状態は要観察です。
さいごに
この記事では、高齢者から介護者への暴言・暴力行為について説明してきました。
尊重されるべき!
間違ってはいないと思います。
しかし
それに固執しすぎることで、介護者のケアをおろそかにするのは間違っています。
高齢者だけでなく、介護をする側も大切にされるべきだと思います。
介護者を大切にすることが、結果として高齢者を大切にすることにつながる
そう感じる今日この頃です(^^)