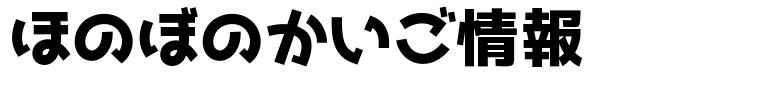投稿者のしんです。
私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。
その後かれこれ10年以上、介護現場で働いています。
2年~3年で、1つの部署を異動してきました。
特別養護老人ホーム、グループホーム、ショートステイをこれまで経験し、今に至ります。
今後のキャリアとしては、「しろくま介護ナビ」を利用して、在宅施設のサービスを経験していく予定です。
日本の介護の現状と課題を、施設介護の観点から学びたいと思っております。
-

-
しろくま介護ナビはどんなサイト?
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後かれこれ10年 ...
続きを見る
介護をするうえで、「人間関係」の悩みは、必ずつきまといます。
私は、長年、介護現場で多くの失敗をしてきました。
その経験を通して、お伝えできることがあります。
こちらの記事で少し楽になると思います(^^)
-

-
人間関係で悩まれている方へ
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後かれこれ10年 ...
続きを見る
この記事では、介護職の介護負担について書いていきたいと思います。
介護をするうえで、どうすることもできない負担はあります。
1日体を動かして仕事をするので、全く疲れなくするのは不可能です。
しかし、反対に負担を軽減できる部分も多くあります。
この記事の内容を知っているのと、知らないのでは感じるストレスは大きく変わります。
ぜひ、最後までご覧ください。
できることなら、新人時代の私にも伝えたい内容です(笑)
~もくじ~
【必読】介護負担は減らせます【知っておくべき4つの方法】

介護負担を減らすとは一体どういうことなのか?
大きくわけると、下記の3つのポイントがあります。
- ストレスを感じる頻度を減らす
- 受けるストレスを軽減させる
- ストレスを発散させる
これら3つのことを意識することで、介護職としてのストレスは大幅に軽減させることができます。

- 言っていることは分かるけど・・・。
- 具体的にどうすれば良いの?
- やり方が分からないよ!
このように感じる方も多いと思うので、具体的なポイントをお伝えしていきます。
これから私が説明する内容は、どれも明日から現場で実践できることになります。
ぜひ参考にしてみて下さい。
明日から実践できる4つのポイントを紹介します
明日からできる4つのポイントは下記です。
- 知識をつけ病気の症状を知りましょう
- 事前準備をしておきましょう
- リスクマネジメント(危険予測)をしましょう
- 一人でみようとしない!
それぞれの項目を詳しく説明していきます。
知識をつけ病気の症状を知りましょう
知識をつけ病気の症状を知るということは、単に「できることが増える」「気をつけないといけない部分を理解する」だけではありません。
介護者側のストレスや疲れを軽減させることもできます。
ご利用者の言動に振り回される
介護で負担に感じる原因の一つです。
私も経験してきていますが、これは本当に疲れるんですよね・・・。
これは「何か事が起こってから対応する」という状態です。
無駄なストレスをなくす
何らかのトラブルが、認知症の影響で出現する行動なら、「〇〇しないで!」は言う意味がありません。
なぜなら、認知症という病気は言語の理解力や状況判断能力が低下するからです。
言っても聞いてくれない・・・。
当たり前です。病気なんですから。
認知症の病気を理解することで、言っても聞いてもらえないならどうやって環境を工夫するかを考えることができます。
無駄なストレスを減らしましょう!
事前準備をしておきましょう
これは、介助に入る際に意識しておいた方が良いことです。
介助は、経験を重ねると慣れていきます。
それは具体的に下のことができるようになっていくからです。
ベテランの介護職の方は、これらを押さえて仕事しています。
- 介助に入る前に必要物品を準備しておく。
- 本人の行動を予測する。
- 介助に入る前にはイメージトレーニングをする。
大きく分けると上記の3つに分けられます。
介助に入る前に必要物品を準備しておく
必要物品は事前に準備しておきましょう
これができていないと、途中でご利用者の側を離れることになり、事故につながるケースも多くなります。
また排泄介助を例にすると、壁などあちこちに便が・・・。ということにもなり、しなくて良い作業も増えます。

本人の行動を予測する
これは、ある程度の知識・経験も必要なので、最初は難しいかもしれません。
また、認知症の方を介護するうえでは全てを予測するのは無理です。
しかし、ご利用者の行動の把握ができてくると、トラブルや事故が起こらないように事前に対応することができます。
本人の性格も含めて、毎日の行動の様子を観察することが大切です。
事後対応が増えると、ストレスはどうしても増えてしまいます。
具体的に認知症で出現する行動には、下記のようなものがあります。
- トイレに座ってもらうと、すぐに立ち歩こうとされる。
- 食べ物以外の物を口に入れることが多い。
- 歩行がおぼつかないのに、自身でそれが理解できず居室内を歩き回ろうとする。
これらの行動が出現する可能性は、100%ではありません。
しかし、認知症である以上、出現しない可能性も100&ではありません。
「もし、こういった行動が出現したら・・・」と事前に考えておくことで、実際にこういう場面に出会ったときに、すぐに対応にうつすことができます。
介助に入る前にはイメージトレーニングをする
これは、介助に入る前に「介助と介助を一連の流れとしてイメージトレーニングする」という意味です。
何を言ってるかわからないと思うので、これも具体例をあげて説明します。
✓具体例1:入浴介助で浴槽へつかる場面
- 足を上げてもらう際、どこに立ってもらうのか。
- どちらの手で、どこの手すりを持ってもらうのか。
- 片足が湯舟に入ったら、次は、どこの手すりを持ってもらうのか。
- 足をどのように動かしてもらい、もう一方の足を上げてもらうのか。
- 湯舟内で立ってもらったら、お尻をどうやっておろしてもらうのか。
- どこを持ってもらい、身体を支えてもらうのか。 等
✓具体例2:車いすから椅子へ移乗してもらう場面
- 椅子をどの位置に、どの向きに置いておくか
- その椅子に対して、車いすをどの位置におくか
- 介護者はどの位置に立っておけばいいのか
- どこをもって立ってもらうのか。
- 立った後、どのような声かけで、足を動かしてもらうのか
- 椅子に座る際は、お尻をそのまま下げてもらうのが良いのか?
- お尻を下げる前に、手を椅子の手すりに移動させた方が良いか?
具体例の1と2をみると、「うわ、そんなに考えなければいけないの!?」と思う方もおられるかもしれません。
その疑問に答えるなら、「事前にイメージトレーニングをする部分が多いほど介助はうまくいきます」ですかね。
正直、介護に慣れた職員(介助がうまい職員)は、ここまで考えている方がほとんどです。
これは、次に説明する、危険予測にもつながっていきますので、日頃から意識して介護することをおすすめします。
いや・・・
介護負担を減らしたいなら、必ずやりましょう(笑)
リスクマネジメント(危険予測)をしましょう
認知症の症状は、進行時期やその人の性格、周囲の環境等により変化します。
これまでにも説明してきましたが、行動の予測がつかないことも多いです。
濡れて滑りやすい床を、全力疾走で駆け抜けることも・・・(; ・`д・´)
本人に、「〇〇はやめましょう!」と説明しても、大半は理解してもらえないか、理解したとしても、すぐに忘れてしまわれます。
環境面を工夫しよう
環境面には、主に2つの種類があります。
それは、「落ち着いてもらうための環境」と「事故を予防するための環境」です。
✓落ち着いてもらうための環境
認知症の方は、精神的に不安定になると、落ち着きなくソワソワと動かれることが増えます。
そうなると、転倒などの事故や、他のご利用者とのトラブルが起こりやすくなります。
そうならないように、本人の精神的なケアは必ず必要になってきます。
落ち着いてもらうための環境と言われてもピンとこないかもしれません。
簡単にいうと「本人が不快と感じること」と考えてみて下さい。
注意ポイント
✓事故を予防するための環境
これは、リスクマネジメント(危機管理)という考え方です。
事故が起こらないように、家具などの物の位置をかえたり、事故が起こりそうな障害を撤去したりすることをいいます。
本人の行動を予測したうえで、危険だなと感じる障害はとりのぞいておきましょう。
リスクマネジメントについて、詳しく解説している記事がありますので、そちらも合わせて読んでみて下さい。
-

-
リスクマネジメントを分かりやすく説明します
しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ...
続きを見る
一人でみようと思わない!
介護者は、どれだけ知識や経験があっても人間です。
疲れやストレスはたまります。
疲れない介護者はいません。
疲れている時は、ケアの質も必ず落ちます。
負担を分散させることを考える
認知症の方は言葉を理解する能力は低下しますが、感情が消えるわけではありません。
介護者の表情や言葉の使い方(声のトーンや大きさ等)で、介護者の感情が伝わります。
「介護者がイライラする」➔「ご利用者の言動が荒れる」➔「介護者がよりイライラする」を繰り返すことになります。
じゃあどうするか・・・。
それは、介護負担を分散させるしかありません。
【私が実践している内容】介護の負担を職員間で分散させる方法

これは、実際に私が現場で行っている方法です。
認知症の症状が強いご利用者がいる場合を例にして紹介します。
朝の申し送り時に職員間でコミュニケーションをとる
まず、ユニットの職員(Aさん、Bさん)に提案します。
「今日ショートステイで〇〇さんが来られてますよね?たぶん一人でみると大変なので、負担を分散させませんか?」と声をかけます。
- 「午前中はAさん、お昼からおやつまでは私、おやつ以降はCさんがユニットのリビングにいる」
こういった内容です。
普段は、こんな職員の配置では動きません。
認知症の症状が強い人を対応する時は、一人でみようとすると職員がパンクするので例外として提案することがあります。
介護施設には、いろいろな形態の勤務やユニット編成があります。
また、ご自身の立場やスタッフの関係性の問題で、難しい人もいるでしょう。
これ通りできないことがほとんどだと思います。
私がお伝えしたいこと!
最後にみなさんにお伝えしたいこと
この記事では、介護職の方にとって介護負担をどうやって軽減させるのかについて書いてきました。
いかがだったでしょうか?
少し分かりにくいかもしれませんが、この記事で紹介した内容は本当に使えます。
実際私が使っている方法でもあります。
職員にストレスや疲れがたまってしまうと、必ずご利用者に影響がでます。
そうなることで、ご利用者にっても、職員にとっても居心地の悪い環境になってしまいます。
自分の体調管理も仕事です。
自分のその日の体調と相談しながら、自分の体調合った働き方を覚えましょう(^^)/
みなさんへお願いしたいこと
ご家族の方の中には、本当にどうすれば良いのか分からない方も多くおられます。
在宅介護は本当に大変なんです。
専門的な知識や技術、実際現場で行っている工夫などをお伝えすることで、少しでもご家族の方を助けて上げて下さい。

- TOPページから、メールアドレスを登録して頂けますと、最新記事がいち早くメールで届くようになります❕