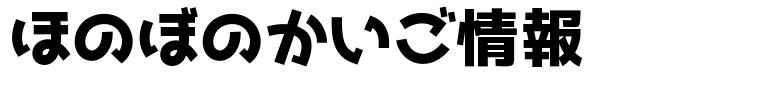みなさん、こんにちは。
投稿者のしんです。
この記事では、「収集癖」をテーマに書いていきます。
- どこ持っていくの!?
- また物がなくなった・・。
- それは危ないから触らないで!

こういった内容について書いていきます。
読者のみなさんへ
「ここにあった物がなくなった」ということも珍しくないですよね(笑)
- 収集癖の症状が分からない
- 収集癖の言動にストレスを感じている
このように感じている方に、参考になる記事になります。
この記事で理解できること
- どんな症状なのか?
- なぜ起こるのか?
- 収集癖への具体的な対応
それでは説明していきます。
~もくじ~
【認知症の理解】収集癖とは?【具体的な6つの対応方法】

収集癖とは一体何なのでしょうか?
どうしてそんなことが起こるかについて説明していきますね。
収集癖とは?
認知症の「行動・心理症状」の中の1つになります。
言葉の通り、自分の物ではない周囲の物を収集される行動です。
介護者からすると、一見「ゴミだ」と思うような物も集めていかれます。
収集癖が起こる原因は?
- 「中核症状の進行」
- 「本人の性格」や「置かれている環境」
これらが合わさり発症するとされています。 しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ... 続きを見る
認知症については、こちらを合わせてご覧下さい。

認知症の症状について解説!
認知症が進行すると、必ず発症するの?
人によります。
認知症の方が全員この症状を発症するわけではありません。
症状は治るの?
「治る」という認識より、その時期を過ぎたら「消失する」という認識に近いと思います。
「症状を治す=認知症を治す」ことになると思いますが、現代の医療では無理とされています。
「治す」ことができないため、「どう対応するのか」が大切になります。
認知症の収集癖の見解
しかし、認知症のない脅迫症の患者と異なり、少し前の自分んお行為を覚えていないことが多いことから、このような収集の場合でも、自分が何を集めてそれをどのようにしたのかは覚えていない。
そのため、本人がいないすきに、新しく収集したものを処分したりすることは、一つの方法である。
日本認知症ケア学会 「改正・認知症ケアの実際Ⅱ:各論」より
介護者が困るポイント
- 必要な物がなくなる
- 不潔なもの増える
- 他人とのトラブル
主にこれらがあります。
介護者からすると、理解できない行動なのでストレスに感じることが多いです。
また、認知症は進行することで、他の症状も重複するので、簡単に解決できるものではありません。
収集癖への対応【6つの方法】

- 情報共有を行う。
- 持っていかれて困る物、危険なものは隠す。
- 原因分析をする。
- 本人がいない間に断捨離。
- 本人が落ち着く環境を考え続ける。
- 協力体制を整える。
介護者が収集癖に困る状態ということは・・・。
- 歩行能力がある。
- 中核症状もある程度進行している。
- 他の行動・心理症状も持っている(徘徊・異食)。
これらのことが予想されます。
そのため、それらを念頭に対応方法を書いていきます。
情報共有を行う
情報共有は必ず必要になります。
そのご利用者に直接関わるユニットの職員はもちろんですが、その方が関わりそうなユニットや事務所も対象です。
少しでも事故や他のご利用者とトラブルが起こらないように、環境を整えましょう。
持っていかれて困る物、危険なものは隠す
ご利用者に「それは置いておいてもらえます?」と伝えても、伝わることが少ないです。
伝わったとしても、記憶障害により長くは記憶が保続しないと思います。
そのため
事前に持っていかれて困る物や、洗剤や漂白剤など異食の危険になるような物は、手の届かない所にしまっておきましょう。
原因分析をする
本人の行動には、必ず「本人しか分からない理由」が必ずあります。
本人の昔の記憶が影響していることも多いですが、本人の世界観を理解し、安心してもらえうように適切に対応していくことが必要です。
ポイント
本人がいない間に断捨離
収集されるのに目的は存在しますが、認知症は物事の判断能力が低下する症状です。
収集した物を、清潔にし保存する等の判断が難しくなるため、衛生的に問題が出てくることも多いです。
その場は本人の思いを尊重し、見守ります。
しかし
その後本人のいない時間で、収集したものを処分することも必要になってきます。
本人が落ち着く環境を考え続ける
これは認知症を患っている方、みなさんに言えることです。
常に「本人が落ち着く環境を考え続ける」ことが認知症ケアでは必要です。
介護者の都合で、行動に制限をかけたり、制止してしまう気持ちもよく分かります。
実際私も、現場でそうしてしまうこともあります・・。
ただ、自分の思いを正確に伝えることができない症状です。
そういう介護者の対応が、逆に本人の精神的不安定を必ず招きます!
注意ポイント
協力体制を整える
上でも説明しましたが、認知症の方は「本人しか分からない理由」があり行動されています。
そのため、行動を無理に制止すると、精神的に不安定になられることも多いです。
利用しているユニット内だけで、本人の問題を解決するのは難しいことも多いため、周囲の協力が必要になってきます。
忙しいのは重々分かります。
ただ、無理な時もありますよね・・・。
私は、そういう人には、その人の上司に話して協力してほしいことをお願いします。
「施設全体でどうやって、ご利用者をみていくか」これが本当に大切です。
まとめ
収集癖をどうにかしたいと考えておられるのなら!
- 症状を正しく理解する
- 本人の状況を正しく分析する
- 落ち着いてもらえる環境設定を行う
- 協力体制を整えるよう努める
このポイントを意識して、対応していきましょう!