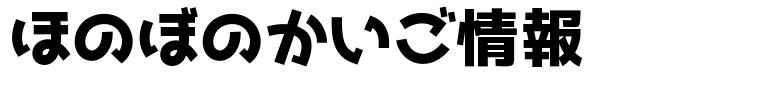みなさん、こんにちは。
投稿者のしんです。
この記事では、「徘徊」について書いていきたいと思います。
- なんでウロウロするの?
- 家からいなくなったらどうしよう・・。
- せめて家の中にはいてよ・・。

こういった思いを持たれている方に、情報をお伝えしていきます。
読者のみなさんへ
在宅で生活されている方は、「いつ本人がいなくなるのか」と不安に思われますよね。
実は施設に入所されている方でも、他のご利用者とトラブルになったり、「離設」といった事故が起こることもあるんです。
- 徘徊の対応の方法が知りたい。
- なるべく家の外に、一人で出ないようにしたい。
- いなくなった時の対応が知りたい。
このように感じておられる方に参考になると思います。
この記事で理解できること
- 徘徊とは?
- 徘徊への具体的な対応方法
それでは説明していきます。
~もくじ~
【認知症】徘徊とは?【対応方法は6つあります】
具体的な対応方法を知るには、そもそも「徘徊」とは、どんな症状なのかを知っておいてもらう必要があります。
そのため、簡単ですが「徘徊」についてご説明していきます。
徘徊とは?
認知症の中でも「行動・心理症状」の中の1つになります。
認知症になり出現する症状は、人によりバラバラです。
認知症の方の症状には、全て「本人なりの理由」があります。
理由はさまざまで「何かを探している」「家に帰ろうとしている」「不快に感じることがあり、その感覚から逃げようとしている」等。
本人の性格はもちろんですが、置かれている場所や状況によっても変わります。
注意ポイント
- 認知症が進行すると、いろいろな障害の影響により、「自分の言いたいことを相手に正確に伝える」ことが難しくなります。
- その2つが合わさることにより、介護者からすると「意味もなくウロウロしている」と問題行動とみられてしまいます。
在宅で生活されていると、「さっきまで家にいたのに、いつのまにかいなくなってる」ということも・・・。
高齢者の行方不明者数からみる現在の日本の状況
まずはこちらをご覧ください。

これは警視庁が発表されている、平成30年の行方不明者数のデータになります。
赤い枠をみて頂いたら分かると思います。
認知症を理由とする行方不明になる方の数が年々増加しています。
こちらが、今後の日本の人口予想推移です。

これは内閣府のデータです。
今後、総人口が減少し子供の数が減ることで、高齢者を支える若者層がいなくなる可能性があります。
医療も今後進歩は必ずするので、認知症が治る病気になる未来も近いかもしれませんね。
しかし
現状、すぐにそういう未来がくるわけではないので、認知症という症状や対応は押さえておく必要があります。
では、徘徊に対してどのように対応していけば良いのか。
説明していきますね。
徘徊に対しての具体的な対応方法

それでは、具体的にどのような方法で認知症の徘徊に対応していけば良いのでしょうか?
詳しく説明していきますね!
➀理由を分析する
「本人が何を思って行動されるのか」本人に話を聞いたり、言動の様子を観察し原因を探りましょう。
トイレを探している?
私の経験上、トイレに行きたくてソワソワされることが多くあります。
- トイレを分かりやすくする等の工夫
- 排泄の周期を観察し、尿意を催されるタイミングでトイレへ誘導
不快感から逃げようとされる?
「気づかない間に排泄を失敗されており、その不快感からソワソワしている」等の不快感。
不快感が「こんなところにいたくない!」という思いにつながることもあります。
昔の記憶を持たれている?
- 「ここは私の家じゃない!」と思われる帰宅願望
- 「そろそろ仕事にいかないと!」という働いていた頃の記憶
これらが影響している場合もあります。
➁他のことに気をそらす
興味をもたれること
その方が興味を持たれるものをしてもらったり、玄関にそれを飾っておく。
それにより、そちらに興味がいき外に出ることが防げることもあります。
役割をつくる
- 洗濯物たたみ、お皿拭き等をお願いする
- 手作業など夢中になれることを探す
➂便利グッズを使用する
認知症の徘徊に対応できる「便利グッズ」は意外と多く売ってあります。 みなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 この記事では、徘徊に対応するための便利グッズを紹介します。 認知症の徘徊の対応にお困り ... 続きを見る
それらを利用し「外にでるのを防ぐ」、「外に出ても見つけることができる」ことができます。

徘徊に対応する便利グッズはこちら!
➃服に名前や連絡先などを記載しておく
服の内側や靴にワッペン等を使用し書いておくこともおすすめします。
一人で外に出られた時に、他の方に「どこに住んでいる、誰なのか」が分かるようにしておくことで、連絡をもらえることもあります。
➄地域との連携
自分一人では気づかない場合もあります。
近所の中の良い方などに、事前に情報を伝えておくことで、地域で見守りできる環境がつくれます。
また、近くの交番や警察とも相談しておきましょう。
いなくなられたら、すぐに捜索にうつってもらいやすくなります。
これまで何度か外に出られたことがある場合は、本人がよく行かれる場所の方と連携しましょう。
万が一外に出られた場合でも、すぐに見つけることができる可能性があります。
➅デイサービスを利用する
担当のケアマネージャーに相談し、デイサービスを利用することも良いです。
デイサービスに行かれている時間は、介護に関して一時考えなくて良い時間になります。
本人にとっても、時々外に出てストレスを発散できる時間になるのではないでしょうか。
外にでた!見つからない!そんな時は。
すぐに警察に連絡しましょう!
一人では無理です。
早めに連絡できれば、本人の移動距離もそう遠くはないので、見つけやすくなります。
さいごに
認知症の方の行動は、どんなに介護に慣れている方でも100%予想することはできません。
必ず周囲との連携が必要になります。
「認知症の人を介護しているなんて、恥ずかしいし知られたくない」
と思われる方も少なくないと思います。
気持ちはお察しします。
しかし、認知症の方の行動は、その人の命に関わることです。
一人では、まず無理と考えて下さい!
信頼できる人・協力してほしい人
気持ちは少しは軽くなるのではないでしょうか(^^)