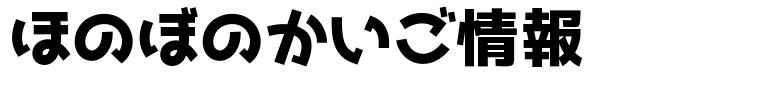みなさん、こんにちは。
投稿者のしんです。
今回の記事では、ご利用者の「帰宅願望」について書いていきたいと思います。
- 何回同じこと聞くの?
- さっき説明したよね!
- うるさいなー!

ご利用者の「そろそろ私帰ります!」という発言。
聞かれることも多いのではないでしょうか?
読者のみなさんへ
帰宅願望の対応は、介護に携わる方は必ずといって良いほどしていかなくてはいけません。
介護現場は、基本的に職員の数がたりません。
その中でどのように対応していけば良いのか。
参考になると思います。
この記事で理解できること
- 帰宅願望の基本的な対応方法
- 疲れやストレスに感じるポイント
- 実用的な具体的な対応方法
それでは、説明していきますね。
~もくじ~
【認知症の理解】帰宅願望の対応【ストレスを減らそう!】

しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 その後 ... 続きを見る
みなさんは、帰宅願望という症状をご存じでしょうか?
帰宅願望とは、認知症の症状の中でも、心理・行動障害と言われるものの1つです。

認知症を理解しよう!
前置き
認知症の症状は、脳の萎縮や脳梗塞、外部からの何らかのダメージ等で脳の機能が失われることで起こります。
よく「認知症は治る」という言われる方もいらっしゃいます。
私の個人的な意見では無理だと考えています。
現代の医療では、上の理由で失われた機能が完全に戻ることはありません。
そのため
認知症ケアは「治療」ではなく「症状に対する対応」を必ず意識しなければなりません。
認知症の症状について詳しく説明されているサイトのご紹介
帰宅願望の基本的な対応方法
帰宅願望の基本的な対応方法は、大きく分けると2種類です。
- 一回一回丁寧に説明する
- 原因分析を行い、環境を考える
詳しく説明していきます。
➀ 一回一回丁寧に説明する
認知症の方は、基本的に記憶障害をもたれています。
たとえ訴えの感覚が5分でも、本人からすると、「毎回初めて尋ねる」と思っておられます。
一回聞いて説明されても、そのエピソード自体を忘れてしまい、また尋ねるということです。
何度も言われて、「無視」したり、「もう!何回同じこと言わせるの!」と介護者側が言っても通じません。
もし、そういう対応をしてしまったら、「不快」という気持ちが残り、より「帰りたい!」という気持ちに拍車をかけます。

本人の気持ちに寄り添い、親身になって相手の話を聞くことが理想です。
➁ 原因分析を行い、環境を考える
認知症の帰宅願望には、夕暮れ症候群のような昔の記憶が出現する場合と、その他に何か原因がありソワソワされる場合があります。
メモ
夕暮れ症候群とは?
夕暮れ時になると、ソワソワと落ち着かなくなる症状です。
日が暮れてくると、家に帰りご飯の支度をしたり、家族が待っているため帰る等の昔の生活リズムの記憶が出現すると言われています。
この対応方法は、夕暮れ症候群以外の理由でソワソワされる場合に必ず行わなければならない対応です。
ソワソワされる原因はさまざまです。
- 不快な感情(尿意・便意、痛い、かゆい等)
- 室温(寒い・暑い)
- 周囲の環境(うるさい・嫌いな人がいる、暇 等)
認知症の方は、自分の思いを自分の口で正確に相手に伝えるのが難しくなります。
本人の言動から原因を分析し、その問題に対して対応する。
そうすることで、本人にとって落ち着くことができる環境設定を行うことができます。
この2点が、基本的な対応方法になります。
ただ
上でも書きましたが、実際介護をしていて「帰宅願望の対応」は、ストレスがたまることが多いんですよね・・・。
私もストレスや疲れは正直たまります。
人間ですからね(;^ω^)
どうやったら介護者の疲れを少なくし、理想の対応をしていけるのか。
ここからは、私の経験を踏まえて書いていきます。
帰宅願望の対応にストレスを感じる理由

ストレスを感じる理由の代表的なものは下記です。
- 何度も同じことを言われる
- 業務が忙しい時に言われる
- 他の方の対応中に言われる
- 事故が起こる危険が高くなる。
基本的にこの4つの理由が、大きいのではないでしょうか。
帰宅願望が出ると、ソワソワされ歩いていかれたり、荷物を片手に持って歩いていかれることもあります。
本人は帰る気持ちになっておられるので・・。
それにより転倒などの事故につながることも少なくありません。
また、本人を対応していることで、ユニットの見守りができなくなり、他の方の事故の危険が高くなることもあります。
施設では、ショートステイで退所される方がいると、なぜか帰宅願望の連鎖反応が・・・。
ということもあります。
そうなると、数人が同時にソワソワされたりします。
それを職員一人で対応することも多いです。
正直とても大変です(;^ω^)
では、私がどのように対応しているのかを書いていきますね。
それはこちらです!
実用的な具体的な対応方法

「事前準備」と「訴えの対応時」に分けて説明していきます!
事前準備は3つ。訴えの対応時は4つです。
事前準備
➀ 帰宅願望がありそうな方の言動を念頭に、業務の優先順位をつける。
違う方の排泄に介入する前に、帰宅願望がでそうな方が落ち着いてもらえるような環境づくりをする。
➁ ヘルプ要請できそうな人とご利用者の情報を共有する。
<
本人の対応とユニットの見守りを、自分一人で行う場合には限界があります。
見守りしてもらうヘルプを依頼する。
➂ 疲れを分散させる
疲れてイライラすることもあります。 しんみなさん、こんにちは。 投稿者のしんです。 私は、新卒で特別養護老人ホームに入社しました。 &nb ... 続きを見る
でも、介護者側の対応が荒れると、ご利用者は間違いなく荒れます。
自分で自分の首を絞めることになります。
こちらの記事で、分散のさせ方を詳しく書いています。
興味がある方は、ご覧ください。

負担は分散しよう!
訴え出現時
➀まずは原因分析する。
分析は、「本人の言動の観察」と「傾聴」からです。
傾聴している時、タイミングをみて「なんで帰りたいと思ったんですか?」と私は聞きます。
けっこうな確率で「〇〇やから、帰ろうと思って」と話してもらえます。
➁解決不可能な場合は、事故が起こらないように意識。
こちらの説明を聞いてもらえない場合や短時間で何度も話される時。
あえて距離を置く必要がある時もあります。
帰宅願望そのものを忘れられるのを待つ場合もあります。
うろうろされる時は、話しかけず見守りながら、少し距離をあけ後ろをついていきます。

➂一人で無理な場合は、ヘルプ要請。
一人では限界はありますからね・・・。
➃意識がそらせる方法を検討
「手持ち無沙汰」が理由で、帰宅願望が出る人もいます。
そういう方には、家事を一緒にしたり、何か手伝って頂ける物を準備したりします。
帰宅願望が出た時の、私の実際の対応を書いてみました。
いかがでしょうか。
施設によっては、できる内容・できない内容はあると思います。
参考なればうれしいです(*'▽')
最後に一つだけお伝えしたいことがあります。
私の周りにも「これをこの時間にしないといけないから」と言う方がいます。
確かに、その時間にしないといけないこともあると思います。
でもね
「その時間にしないといけない」と思い込んでいるのは、その人だけだったりします。
何が言いたいかというと・・・。
介護をするにあたり、柔軟な発想が必要になります。
- 「これは〇〇だ」
- 「これはこうしなければならない」
意外とそんなことないんです。
せっかくの機会なので
日頃の自分の働き方を見つめなおす機会にしてもらえたらうれしいです(*'▽')