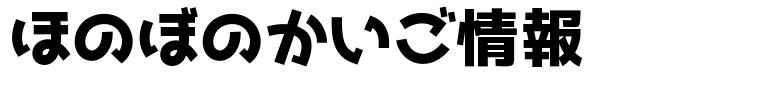みなさん、こんにちは。
しんです。

この方にとって何が大切が分からない・・。
一人で担当するのは、不安だなー。
こういった疑問にこたえていきます。
この記事では、ご利用者のケアを考える際、どのような点に注意して考えていかなければならないのかを説明していきます。
初めてご利用者の担当を持った方や、現在担当をもっているご利用者のケアを見直したいと思っている方に参考にしてもらえると思います。
では、いきましょう!
~もくじ~
【重要】ご利用者のケアの検討方法【間違えたケアをしないための方法】
下記の方法を順番に考えていくことが、ご利用者のケアを考えることになります。
- 現状の確認
- ご本人とご家族の要望
- ケア目標の確認
- 目標達成できる具体的な方法
- チーム内でのケアの統一の方法
1. 現状の確認
ご利用者の現在の状態を確認します。
確認する項目は下記です。
- 性格・コミュニケーション面
- 認知度
- 他の方との関わり
- ADL(日常生活動作)面
- 1日の過ごし方
- 健康面
- 身体健康面
・食事
・排泄
・入浴 等
・起床されてから、日中をどのように過ごされているか。
・夜間帯の様子
・既往歴
・現在かかっている病気・症状
・服用されている内服薬
・麻痺の有無
・関節の拘縮の有無
・褥瘡や体の痛みの有無
・皮膚疾患の有無
総合的な情報が必要になります。
このアセスメントされた内容をケアプランに落とし込むことになります。
施設によっては、ケアプランの作成を現場の職員がしているところもあります。
ケアマネージャーだけでなく、現場の職員も知っておく必要があります。
2. ご本人とご家族の要望
「今後どのような生活を送っていきたいか」を確認しましょう。
介護職は、ご本人とご家族のニーズに沿うサービスを提供する仕事です。
私の経験の中で、時々、業務をまわすことに意識がいきすぎて、ご利用者の生活が後回しになっている場面がありました。
勘違いしないようにしましょう!
✕ 業務をまわすために、ご利用者のケアがある
〇 ご利用者のケアに合わせ、業務を調整する
3. ケア目標の確認

簡単にいうと、総合的な支援内容です。
基本的には、ご本人やご家族の要望に沿ってサービスを提供していきます。
入所している施設によっては、望まれているサービスを全て提供するのが難しいこともあります。
それらのニーズを、生活されている場でどのようにサービスにつなげていくのかを考えることが大切です。
具体例1
「静かに生活したい」
●ご家族のニーズ」
「体調を崩さずに生活してほしい」
・総合的な支援内容:「ご本人の時間を大切に、怪我なく生活できる」
具体例2
情報収集できず(コミュニケーションが難しい)
※本人の性格が「楽しいことをすることが好き」
●ご家族のニーズ
「落ち着いて生活してほしい」
・総合的な支援内容:落ち着くことができる環境で、楽しみを持って生活できる
具体例はとても簡単にかきました。
「いやいや、それは違うだろ」という意見もあるかもですが、なんとなくイメージしてもらえることができたら、ありがたいです。
私は、介護現場でケアプランを作成していましたが、この1文を考えるのに1時間くらいかかっていました・・。
その1文で、ご利用者の人生が左右されると思うと、怖くて(;^ω^)
本当に難しいです。
4. 目標達成できる具体的な方法
この内容は、主に現場の職員がチームとして動く内容になります。
具体例
- 1日1回〇〇をする。
- 毎週月曜日に〇〇をする。 等
意識しなければならないこと
ご利用者へのサービス内容を考える時は、必ず、ケアの目的を意識して下さい。
そして、チーム内でも「そのご利用者のケアの目的」を共有してください。
これは本当に大切です。
「ケアの目的」ときいても、具体的にどういうこと?と思われる方もおられると思うので、私が過去に実際に経験した事例をだして、詳しく説明します。
5. チーム内でのケアの統一方法
事例をもとに、説明していきます。
キーパーソン:Aさんの嫁(面会頻度は高い)
食事は、全介助。リビングで車いすに乗車して提供。
起きていると、痛みの訴えが強く、食事時間以外は、居室で横になり過ごされている時間が多い。
病気の症状の影響もあってか、終日腰や足の関節などに痛みの訴えあります。
痛みのが強い時は、涙をながしながら痛がられる。
毎食後、内服にて痛みのコントロールをしているが、痛みの完全消失はできない。
「こんな体になった自分が情けない」
●ご家族のニーズ
「痛みを軽減した生活を送らせてあげてほしい」
「寝たきりになるのは、嫌」
情報が足りないところもあるとは思いますが、
みなさんは、どういうケアを提供してあげればいいと思いますか?
ご本人の思いは痛いほどわかります。
私自身も、同じ状況なら同じことを思うはずです。
痛みの訴えが一番少ないのは、ベッドで横になっている時。
今後トイレ誘導や入浴方法などどうしていくのか・・。
どんな対応にもメリット・デメリットは存在します。
ご利用者のケアを行う時は、必ず両方の観点を考え、デメリットを回避・軽減できる対策も同時に検討する必要があります。
また、ご家族が正しい病気の理解ができていない可能性があるため、再度分かりやすいように説明する必要もあると思います。
✓ケアの提供方法の統一は不可能な時もある
日頃介護をしていて、ご利用者のケアの判断に迷うことはたくさんあります。
しかし、チーム内で全てを完璧に統一することは不可能だと思っています。
なぜかというと、「全て」には、介護者の価値観が大きく影響してくるからです。
「しんどそうな時は〇〇しましょう」
「痛そうな時は〇〇しましょう」
これらは、数値に表せません。

✓ケアの「目的」の共有が必要
介護現場は臨機応変に対応することが、求められます。
そのため、ご本人やご家族のニーズ、そしてケア目標をチームで共有し、ケアの目的は明確化しておきましょう。
同時に、体調不良や事故が起こる可能性が高いことに関しては、「してはいけない対応」として、決めておきましょう。
介護のケアをすすめることを、違う例で例えると・・・。
この時、チームで共有するのは、「〇月〇日〇時に北海道に再集合する」という目標です。
そのため、北海道に行く手段は指定しません。
人によって、飛行機で行く人、電車で行く人、車で行く人などばらばらになるでしょうね。
でも、指定された日時に集合します。
目標は達成できますよね?
もし手段まで決めてしまうとどうでしょう?
高所恐怖症の人は、飛行機にのれません。
車酔いする人は、車の長距離移動は地獄です。

まとめ
- ケアの内容は、ご利用者のケアを考える方法です。
- ケアには、統一できない内容があります。
- 「してはいけない対応」は統一する必要がある。