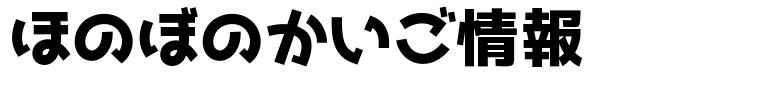みなさん、こんにちは。
しんです。

最近、このご利用者食事食べにくそうだなー。
食事中むせてることをよく見るなー。
高齢になると、体の機能が低下していくため、どうしても生活に支障が出てきます。
この記事では、高齢者の食事に関して、どのように考えていけばいいのかを説明したいと思います。
✓本記事のテーマ
【高齢者の食事】状態変化に合わせた対応方法
✓記事を読んでくれている読者さんへ
人間は、高齢になっていくと体の機能が低下します。
それはしょうがないことです。
食事を口から食べるということは、ご利用者の人生の満足度を上げたり、体調を維持、または良くする点において、とても大切なことです。
この記事を読んで頂ければ、ご利用者の状態が変化しても実践できる「少しでもおいしく食事を食べてもらうケア」、「体調を崩さず食事を食べてもらうケア」が理解できると思います。
では、本題にうつります。
~もくじ~
食事を食べる行動の手順を確認しよう
簡単に説明します。
- 五感を使って食事を認識する
- お箸などを使用し、食事を口に運ぶ
- 口の中の仕組みの理解する(かむ、塊をつくる、飲みこむ)
それぞれの項目の説明と、その項目の機能が低下した時の対応をお伝えします。
➀五感を使って食事を理解する
食事が運ばれてくると、おいしそうなにおいが漂ってきます。運ばれた食事をみて「おいしそうだな」
「どれから食べようかな」と、どんな食事が口に入るのか等、脳が食事を食べる準備を行います。
一番大きい情報は、食事の色合いなど目から入る情報と言われています。
視覚に障害がある方への対応
・よく視覚障害のある方には、クロックポジションで説明する方法があると言われていますが、
高齢者で視覚に障害がある方は、覚えることが難しく、あまり実用的ではない思います。
クロックポジションとは、時計の位置で説明することをいいます。
目の前の置かれた食事に対して、「3時の位置にご飯があります」「9時の位置にお味噌汁があります」等です。
実用的な方法としては以下の方法です。
- 食事を、手にとりやすい位置に置く。
- 目の前に置く食事の数は、多くて3つ。
- 時々、困っていることはないか声をかける。
食器の配置や盛り方など、本人と相談し決めるのが良いです。
五感についてや、その他食事の時に観察しなければならない項目を、こちらの記事にまとめています。
こちらも見てもらえれば、より食事の関するコツが分かると思います。
➁お箸などを使用し、食事を口に運ぶ
食事が運ばれると、手でお箸やスプーンをもち、食事を食べます。1回で口に入れる量は、自分の好きな量を
自分のペースで決めています。
また、頭では「食事を食べている」という認識をします。
体の機能が低下すると、食べこぼしの原因になったり、一回で口に入れる量が多く、食事を喉につめさせたりという問題がでてきます。
姿勢の見直し
食事の正しい姿勢は、画像をみて下さい。

人により、食べやすい姿勢は違うので、これを基本に本人と相談し試して下さい。
食事を食べる姿勢が、アゴがあがり、上を見上げるような姿勢になっておられる方がいます。これは誤嚥の原因になるので、要注意です。

ポイントは、前かがみの姿勢です!
自助具の検討
自助具を検討する場合は、施設なら理学療法士や栄養士の職員に、在宅なら担当ケアマネージャーに相談してみて下さい。
傾斜がかかった食器や、スプーンの先を噛んでしまう方へのスプーンなどはアズワンやアマゾンなどの、ネットでも購入できます。
リンクを貼っておきます。気になる方は見てみて下さい。
Navis(アズワンオリジナルブランド)公式サイト:https://axel.as-1.co.jp/contents/nv
Amazon.co.jp(アマゾン)公式サイト:https://www.amazon.co.jp/
➂食事をかみ、塊をつくる、飲みこむ
口に入った食べ物が大きすぎても、小さすぎてもうまく飲みこめません。食事をかむことで、適度な大きさにします。かんだものは、唾液と混ぜ合わせながら塊になり、舌をつかって喉の奥におくられます。
口の中がぱさぱさだと、塊をつくることが難しくなるので、適度な湿り気が必要です。
食べ物が口に入った後の「かむ(咀嚼)」「塊をつくる食塊形成)」「飲みこむ(嚥下)」のそれぞれの機能が低下していた時に行う、具体的な対応方法を下に書いておきます。
食事形態の検討
施設によて主食なら米飯・軟飯・粥・ペースト粥、副食なら常食・一口大・きざみ食、ムース・ソフト食、ペースト食などさまざまです。
「かむ」機能が低下した方には、刻み食など最初から細かくした状態で提供します。
デメリットとしては、口の中でバラバラになりやすいので、誤嚥するリスクがあります。
かつお出汁をお湯で溶かし、それに少しトロミをつけます。
それを食事と混ぜ合わせることで、まとまりやすくなります。
水分への工夫
水分によるむせ込みが多くなってきたら、水分にトロミをつけたり、お茶ゼリーを考えます。
人が何かを飲みこむ時の口の中の仕組みは、今回は書きませんが、飲みこむ反射の機能が低下すると、飲みこもうとしたものが、勝手に気管のほうへ流れ込んでしまいます。
トロミやゼリーにすることで、水分にまとまりをつけ、気管に入るのを予防できます。
~豆知識~
日頃のコミュニケーションはリハビリにもなるんです。
何のリハビリかというと、舌です。
これまでの説明でも分かるとは思いますが、舌は食事を食べることにおいて大切な役割を担っています。
よく話す人ほど、舌の筋肉がしっかりしており、誤嚥をおこしにくいと言われています。
最後に
今回説明した対応方法は、体調崩さないように生活してもらうために検討すべき内容です。
しかし、ご利用者にもよりますが、「おいしそうではない」「おいしくない」と言われる方も多く、これらの対応が逆に食欲低下につながることも多くあります。
自分の口で、自分の気持ちが言葉で伝えられない方のケアは特に難しいです。
「楽しくおいしく食事をする」対応と「体調を崩さず生活を送る」対応
この2点に関して、両方のメリット・デメリットを念頭に食事ケアを考えてあげて下さい。