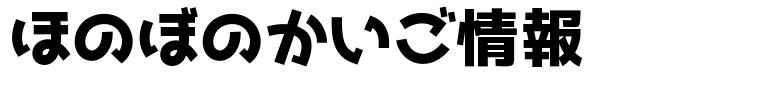みなさん、こんにちは。
しんです。

そもそも食事介助って何?
食事の時の観察ってどこをみればいいの?
こういった疑問に対して、コツを教えていきたいと思います。
✓本記事のテーマ
高齢者の食事の観察【2つの重要なポイント】
✓記事を読んでくれている読者さんへ
この記事を読んで頂くと、現場で働く職員が、食事の際どこを観察しているのか、どういう対応をしているのかを理解することができます。
介護負担や事故のリスクを減らすだけでなく、楽しみの時間を提供できることにもつながります。
高齢者は、若い人と比べると、行動量が少なく、体調を崩しやすいです。
後述する内容は、全ての人に当てはまるわけではありませんが、注意するべき内容は参考になると思います。
それでは、さっそく本題にいきましょう。
食事介助をする際の2つの重要な観察ポイント
- 周りの環境への配慮
- 本人の体調

詳しく説明していきますね!
➀周りの環境への配慮
「そんなこと分かってるよ!」と思う方もおられると思いますが、意外と職員が気づいていないことが多いです。
最近では、ユニット型の特別養護老人ホームが多いですが、ユニット型といっても共同生活をする場です。
そのご利用者が、ご自宅で生活されていると受けないような刺激が、周囲には多く存在します。
人間の五感
・人間は外部から情報を得ようとする時、五感が働きます。
五感とは、視覚(みる)・聴覚(きく)・嗅覚(におう)・触覚(さわる)・味覚(あじわう)のことをいいます。
ご利用者が食事を食べらるれる際、不快に感じたり、気が散ったりと食事に集中できないか環境になっていないか、注意を払いましょう。
具体例があると分かりやすいと思うので、下の項目を参考にしてみて下さい。
- 視覚:他のご利用者の言動、料理の中に嫌いな食べ物がある、職員が食事中に回りでバタバタしている 等
- 聴覚:他のご利用者の言動、テレビや音楽の音の大きさ 等
- 嗅覚:職員が他のご利用者の排せつ介助を行い、その匂いがリビングに充満している 等
- 触覚:食事が冷めている 等
- 味覚:食事の味が、本人の好みと合っていない 等

ご利用者からすると、職員の言動も環境の一部!
➁本人の体調
食欲がわかない、眠たいなど若い人でも抱える問題から、発熱・血圧の変動などの悪化する可能性のある
体調不良など、原因はさまざまです。
「食欲がわかない」という原因一つとっても、「日中ずっと寝ている」「食事の好き嫌い」「そもそも体力が低下し、
食事を食べる行動自体がしんどい」などさまざまな原因があげられます。
そのため、物事の判断をする際に重要なのは、原因を一つに限定しないことです。
また、「もしかしたら、〇〇かもしれない」と感じたら、「なぜ〇〇と思ったのか」を説明できるようにして下さい。
その〇〇という判断が違っていても、その理由で違う原因が見つかるかもしれないからです。
優先するべき問題
・これは、本人にとって食事をとることよりも、優先して解決したい問題がある場合です。
「気温が寒い・暑い」や「痛み」、「かゆみ」など、本人にとっては深刻な問題です。
気温の調整に関しては、衣類で調整はしやすいですが、「痛み」や「かゆみ」は医療分野に
相談し、医療的な視点からのケアが必要になる場合もあります。
食事量が少ないことは、体調崩す可能性を高めることにもなりますので、日頃から医療分野の方に
相談・報告はしておきましょう。
日中の活動量を上げる働きかけとしては、レクリエーションやリハビリ、体操などの取り組みの他に、
その方の生活の中に、体を使う時間を設定する「生活リハビリ」や「ご利用者の役割づくり」があります。
具体例をあげておきます。
生活リハビリ
- 手すりを持って立ってもらった際少し長めに立ってもらう
- 食事席を居室から少し遠い位置に設定する
- 自分のいる場所から離れたトイレを使用してもらう 等
役割づくり
- 施設やユニットの玄関にポストを作り
- 毎朝取りにいく習慣を作る
- 花の水やり、掃除、食器洗いなどの家事を一緒にする 等
食事形態や、嚥下の使用についての記事も書いています。
こちらのリンクからどうぞ(-ω-)/
まとめ
- 周りの環境人間の五感を意識する。
- 職員の言動も環境の一部。